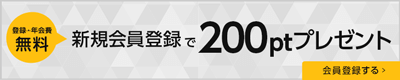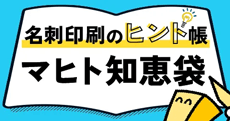印刷用語集
ISBN
国際標準図書番号の略。
市販する書籍コード番号をつけ、その流通合理化をはかったもの。番号は10桁から成り、国籍コード(日本は4)、出版コード、分類コード、製品コードを含み、コンピューターの読み取りによって、その書籍がどこの出版社から出版されたどのような本かなどがわかる。一定のルールに従って書籍に印刷する。日本では昭和57年から使用を始めた。ICカード
銀行カード、クレジットカードなどのプラスチックカードにICチップを内臓したカードの総称で「スマートカード」「チップカード」とも呼ばれる。カード自身が判断機能を有するので、磁気カードに比べてセキュリティー性が高く、データ記憶容量も大きいことから金融、流通だけでなく、医療、教育などの多くの分野でのさまざまな利用形態が期待されている。名刺にも今後ICカード入り等が出てきてもおかしくないのかもしれません。
アウトラインフォント
文字の形状をその輪郭線により定義されたフォント。出力の際には輪郭線より文字を型どり、その内側を塗りつぶすことで文字を表現する。弊社でも名刺のデザインで文字のアウトラインは必須の作業となっております。
亜鉛網版
亜鉛版を腐食して線画と平網とを同時に形成した凸版印刷の原版。亜鉛凸版の版種のひとつ。名刺の印刷にはあまり利用されていない。
亜鉛凸版
亜鉛板を版材とし、写真製版法にて硝酸で腐食して版面を形成した活版用の原版。
青焼き
ジアゾ感光紙によるポジーポジタイプの複写で、写真原版のレイアウトや文字のチェックを目的とする校正に用いられる。ジアゾ感光紙は非常に感度が低いため焼付けに時間がかかることと、寸法安定性に問題があるが、きわめて安価にしかも容易に複写することができる。
あおり出し装置
手差しによる簡単な印刷機の多くに採用される排紙装置。
赤字
印刷物の校正刷りに書き込んだ訂正文字や校正記号。一般に赤鉛筆か赤のサインペンで書き込むので赤字という。弊社のシステムでは、デザインツールによりお客様自身にご確認いただいている為、このような赤字作業が必要ありません。
あじろとじ
無線とじの製本様式の一種で、本文背側を折りの工程でスリットまたはスロット形状の切れ目(カット)を入れ、接着剤で固定する方式。カット部から接着剤が浸透し、接着面積が無線とじに比較し増加するので接着強度が強い。
あそび紙
本の中身の前後に入れて体裁をととのえる紙。一般には本文と同質の紙であるが、色上質などや印刷がされている場合もある。
頭合わせ
天側と天側を付け合せて組み付けること。主に左開きの本に使用され、横組の版が一般的。
あたり罫
完全原稿として台紙を作成する際、写真版の入る位置。平網の伏せ込み範囲、ベタ刷りの境界線などを示すために台紙に書き込まれる仮の罫線。集版段階で見当てとして用いられたのち削除され、印刷のさい現れない。
厚紙
厚さ0.15~0.23mmの、こしの強いかたい板紙の総称。
圧縮性ゴムブランケット
ゴムブランケットには、ソリッドタイプと圧縮性タイプがある。圧縮性タイプのものは表面ゴムの下に弾力性のよいミクロスポンジゴム層があり、圧力を加えても変形が少ない。現在オフセット印刷用としては圧縮性のものが一般化している。
圧胴
圧を加えることでインキを版あるいはブランケットから被印刷体に転写する印刷方式において、圧力を加えるための胴。
圧胴洗浄装置
オフセット枚葉印刷機で、圧胴の汚れを自動的に洗浄する装置。
あて名印刷機
郵便はがき、封筒などにあて名を印刷する機械で、日付けや番号の印刷装置を備えたものもある。宛名以外にも安価、簡便なことから店名の印刷、繰り返し作成する伝票類や社内の連絡文書の印刷などに使われている。日本では謄写印刷方式が一般的
アート紙
コート紙の一種で、高級印刷用に多く使用される。
アートポスト
はがき用のアート紙であり、坪量250g/平方メートル程度の厚紙。主に絵はがきや私製はがきなどに使われる。
アニリン印刷
フレキソ印刷のこと。初期にアニリン系染料をアルコールに溶かしたインキで印刷したのでアニリン印刷と称した。
アフタータック
印刷終了後、ある時間の経過の後でも強い圧力を加えると印刷面に粘着性が残っていることが認められる状態。
網掛け
印刷物で網階調を再現するため、写真などの連続階調を大小の網点に変換する作業。製版カメラやスキャナーで分解された連続階調のあるモノクロ画像に網目のついたフィルムを掛け合わせ撮影することで、連続階調が網階調に変換される。
網掛けスキャナー
網点化された色分解版を作成するカラースキャナー。連続調スキャナーと異なり、網掛けする機能をもつ。
網点
網ネガ、網ポジ、網凸版およびその印刷物にあらわされる点。点の大小により原稿の濃淡を表す。
網点階調再現
写真などの連続階調を、印刷で網階調により表現されること。
網点形状
階調再現に用いる網点の形状。ラウンドドット、スクエアードット、チェーンドットなど多くの種類がある。
RGBカラーモデル
色の特性を示すカラーモデルの一つ。一般的にはHSV(色相、彩度、明度)、RGB(赤、緑、青)、CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、墨)などのモデルが使われるが、その中で光の3原色を用いたのがRGBモデル。これは3つの原色を加えあわせることで白色が作られることから加法混色ともいわれる。
合わせ丁合い
折丁数の多い本の場合、1回の丁合いでは取りきれないため、2回以上に分割し丁合いしたものを最後に合わせること。
安全インキ
小切手、証券、紙幣などの改ざん、偽造防止を目的として用いられるインキ。
安全紙
紙幣や有価証券などの偽造変造の防止を目的とする紙。
板紙
厚さ0.3mm以上または坪量100g/平方メートル 以上のいずれかにはいる紙で、比較的かたく、腰が強い。ダンボール原紙、黄板紙、白板紙、チップボール、色板紙、建材原紙などがある。
一部抜き
製本開始前に表紙、本文、見返し、扉など、1冊の本を構成する部品を取り揃えること。これにより作業指示書との照合を行い、丁合い順序などの間違いを事前に防ぐことができる。
いちょう
製本用具の一種で、表紙のみぞの焼付けなどに使用されるこて。
1回転印刷機
版盤1往復に対して圧胴が1回転する円圧印刷機。
糸かがり
製本の折丁を1折ごと糸でとじ合わせること。糸かがりは家庭用ミシンと同様に針と糸で折丁背に糸を通しながら各折丁をとじ重ねる。
EPSファイル
1ページの組版情報を記述するポストスクリプト言語プログラムで、通常、別のポストスクリプトの記述の中に組み込むことができる。ポストスクリプト言語で書かれたデータを異なるアプリケーション間で使用するために作られたフォーマット。
イミテーションアート紙
印刷適正を特にあげるため、パルプに多量の填料を配合して抄造し、強光沢仕上げを施した印刷用紙。
イメージスキャナー
一般的には、三次元計測や衛星画像などに代表される、対象物をディジタル画像データとして入力する装置をいう。印刷分野においては、スキャナーやカラースキャナーと同じ意味に使われている。
イメージセッター
DTPなどで作成したデータをフィルムや印画紙に印刷するために使用される高解像度プリンターの一般呼称。
色合わせ
指定色の見本に合わせてインキを作ること。普通、見本の主体色を判断しこの主体色のインキを中心に他の色のインキを混ぜて作る。
色浮き
アカ浮きを抑えるというように用いる。画像中のある部分に別の色が感じられて本来の色でないと思われるときに使う。
色温度
黒体放射の分光分布が、その黒体の温度によって一意に決まることを利用し、ある放射光の色度をこれと同じ色度の色光を放射する黒体の絶対温度で表したもの。
色温度計
光源の色温度を近似的に計測するための計器。光をフィルターで赤、緑、青成分に分け、この強度比から色温度を算出する。
色校正
色指定した部分がその通り印刷されているか確認、チェックする作業。写真版などが正しい色や調子で再現されるような製版がなされているか、校正機などで行うのが一般的。
色校正刷り
色校正により印刷された印刷物
色再現
多色印刷、カラー写真、カラーテレビジョンなどで、元の色を再現すること。
色指定
文字、イラスト、図形などに着色を行う場合の指定。割付け指定紙上の着色を行う部分に引き出し線でCMYKの各網%を明記する。または各インキメーカーで作成されている色見本帳を添付して指定が行われるのが一般的。通常、指定ない場合はKのベタが基本。
色修正マスク
マスキング操作により色修正するためのマスク。ポジおよびネガの2通りがある。
色分解
カラー原稿を印刷するために、原稿の各色をイエロー、マゼンタ、シアン、およびグレーバランスを整えるためのブラックの各成分に分けること。レンズまたは光源にフィルターをかけ、パクロフィルムに撮影する。
色ぼかし
印刷物のハイライトからシャドーまで連続的に平網の濃度変化をつけたもの。
色補正フィルター
写真撮影したり、カラー原稿を複製しカラーフィルムを作るさい、元の原稿の色を調整するために用いるフィルター。
色分かれ
顔料が複数種混合されたインキにおいて、インキ表面に一種類の顔料が浮いて異なった色が現れる状態。顔料の比重の差。分散度の差があるインキの内部対流現象によって起こる。
印画紙
写真印画を作る感光紙。おもにハロゲン化銀乳剤を紙面に塗布したもので、現像印画紙と焼きだし印画紙に分けられる。
インキ出しローラー
インキ壺を構成するローラー。これが少しずつ回転し、ブレードとの隙間からインキを導き出す。インキ出しローラー上に形成されたインキ皮膜はインキ移しローラーに間欠的に接触し、インキ練りローラーへ転移される。
インキ着けローラー
版面にインキを着けるローラー。版面に均一なインキ膜を形成するために、直径の異なる数本のローラーで構成されることが多い。
インキ壺
印刷機においてインキをためておく部分。オフセット印刷機では、回転するインキ出しローラーとブレードとの隙間を複数の調整ねじで変え、印刷幅方向のインキ膜厚を調整する。
インキ練り盤
インキをへらで練ったり混合したりする板。おもにオフセットインキの特色の調肉に使われる。
インキ練りローラー
インキ移しローラーからインキ着けローラーまでの間のローラーの総称。インキ壺からのインキが版面へ供給されるまでの間に、一部ローラーを揺動させてインキを練り、インキの流動性を保つ働きをする。
インキ粘度コントローラー
おもにグラビア印刷、フレキソ印刷で使用される、印刷中のインキの粘度を一定に保つための装置。
インキの裏回り
スクリン印刷において、不良の原因となる現象の一つ。インキがスクリン版の画線部周囲ににじみ出す現象。
インキプリセットシステム
オフセット印刷において、インキ壺のインキキーおよびインキ出しローラーの回転量を、印刷開始前に自動的にセットするシステム。
インキべら
印刷インキを練ったり、インキ壺を交換したりするときに用いる鋼製のへら。
インキローラー
インキを練ったり、版面にインキを着けたりするために用いるローラー。鉄芯に厚くゴムを被覆したゴムローラーが一般的。
印刷圧
印刷のさい、版面またはブランケット面のインキを紙面などの被印刷面に転移させるために加える圧力。略して印圧ともいう。
印刷インキ
着色材としての顔料または染料をビヒクルに分散し、必要に応じてワックスコンパウンド、ドライヤーなどの補助剤を加える。
印刷適性
良好な印刷の仕上がりに欠くことのできない被印刷体およびインキ、ロールなどの印刷材料に求められる性質。被印刷体の代表として紙があげられる。
印刷適正試験機
印刷工程に使用される材料が備えるべき性質を評価するための試験機の総称。
印刷版
画線部と非画線部からなり、画線部のみに印刷インキを着け、被印刷体もしくはインキ間接受理体にインキを転移させるもの。
印字
一般には紙や印画紙、フィルムなどに文字を像として出すことをいう。実際にはワープロなどで紙に文字を打ち出す。
インスタントレタリング
透明なシートに特殊な方法で印刷、加工され、上からこするとシートからはがれ転写される文字や記号などのこと。通称“インレタ”と呼ばれる。
インディアペーパー
辞書、聖書などに使用される20~30g/平方メートルの薄葉紙。不透明で、しなやかさをもつことが要求される。
インフィードローラー
巻き取り紙を用いる印刷機や加工機において、給紙部から印刷部または加工部へ向かうウェッブの張力変動を少なくするように制御し、品質を安定させるためのシステム。
インフィードローラー
巻き取り紙を用いる印刷機や加工機において、走行紙を給紙部から印刷部に送るために設けられた駆動ローラー。
インライン印刷機
印刷ユニットごとに圧胴を備え、グラビア印刷機のように直線上に配置したフレキソ印刷機。巻き取りのほかシート印刷も可能である。印刷ユニット間の距離を確保できるので、乾燥ユニットを組み込むことができる。
ウイジウイグ
入力から出力まで統合した文書編集制作システムに関する概念。
ウェット印刷
多色刷印刷機において、2色以上を連続的に印刷する際に、1色印刷した直後、まだそのインキが乾かないうちに、次の色を刷り重ねる印刷のこと。
ウェットトラッピング
多色刷の印刷工程において、濡れている先刷インキの上に次のインキが転移すること。先刷インキは印刷の瞬間、印圧によって表面粘度が上昇し、次のインキを捕らえやすいが、浸透の少ない紙、浸透の遅いインキ使用の場合は2~3色の先刷ベタがある場合はその後から印刷されるインキとの粘度差が少なくなり、転移度合いが小さくなる。そのため後刷りインキほど膜厚を厚く印刷できるようなインキ濃度、印刷面積比から判断して刷り順を判断する。
ウェルダー加工
熱可塑性樹脂を密着する技術の総称。一般的には高周波、あるいは超音波を利用した溶着をいう。
ウォーターマーク
オフセット印刷において、版に供給する水の量が多いとインキの版への転移が抑えられ、水の過剰分が筋状に濃度を低下させた不良印刷物をあすことがある。その濃度の低い部分をいう。
ウォーターマークインキ
すかし用インキ。アラビアゴム液をグリセリンに混合した水性低揮発性インキが一例であり、ゴムまたは金属版を用いて印刷する。
ウォッシング
オフセット印刷において、湿し水とインキがロール間で強制攪拌作用を受け、顔料の一部が水に移ることをいう。
浮き出し印刷
雌型と雄型を用いることにより、印刷と同時に画線部を浮き出させる印刷方式。
浮汚れ
インキまたはインキ中の顔料が湿し水に浮いたり、懸濁したりすることで、版面上に発生するオフセット印刷の汚れ。
打返し
ページ物を印刷する版を組み付けるさいに、表裏にあたる版おを同時に組み付けて用紙の片面に印刷、それを左右逆に裏返し、もう片面に印刷する方法で用紙1枚で2部印刷可能となる。
内校
内校正の略。印刷会社などで校正刷りを発注者に渡す前に印刷されたカラーの色調、誤字、脱字、などをチェックするために行う校正。
打抜き
紙器加工において、印刷の終了した板紙を所要のカートンブランクに打ち抜き、筋付けを行う工程。
埋まり
印刷時に生じるトラブルの一つ。ネームおよび写真のシャドー部の非画線部に紙粉またはインキ顔料が埋まり印刷再現トラブルが生じる現象。
裏移り
積み重ねられた印刷物の状態で生じるトラブルで、用紙表面または裏面のインキがその反対面に転移する現象。
裏カーボン
数枚にわたって複写を行う伝票などで、複写必要箇所にあらかじめカーボン印刷されている状態。
裏白
紙の裏に印刷されてないページ。本によっては扉、目次、中扉などの表面に対して裏は白になることが多い。
裏白掛け
表側だけ印刷して裏が印刷されないような、版面の掛け方。
裏刷り
透明なフィルム素材への印刷で、フィルム素材を介して印刷物を見る場合に用いる。印刷は絵柄の向きや色の刷り順を逆にする。これにより、印刷面の摩耗、汚れなどが防止できるため、耐久性の必要な印刷物に適する。
裏抜け
表に印刷したインキの中の成分の一種が紙の裏ににじみ出る現象
裏版
印刷するときに、用紙の裏面に印刷する版。
エアーシャフト
印刷機の巻き出し、巻き取りに使われるウェブ用シャフトの一種。
衛星工場
新聞の製作において、主工場から離れた場所に分散して設置される新聞印刷工場。
A列本判
わが国の標準原紙寸法の一つで、625×880mmの寸法。
エコマーク
環境への負担が少なく、環境保全に役立つと認められた商品に付けられるマーク。
エッジガイド
巻き取り紙を用いる印刷機や加工機において、走行するウェッブの耳端をエッジセンサーで検出してウェッブの左右位置を制御する装置。
エッジ強調
画像処理や、光学処理によってエッジに濃淡のレリーフを付け輪郭を強調すること。
エッチ液
オフセット印刷の湿し水に添加して使用する液。
エッチ処理
平版における不感脂化処理のこと。
FMスクリーン
網点を構成するマイクロドットが、画素値に比例した数だけランダムに配置される網点形成法。
エマルジョンインキ
溶剤型または油性インキを水と混合し、W/Oエマルジョンとしたインキ。
MICR
磁気インキを用いて印刷した文字、記号を磁気的に読み取る装置。
MC紙
抄紙機上で片面10g/平方メートル 程度の塗料塗布加工を施した高級印刷用紙。原紙には、中・上質紙を使用する。
円圧印刷機
平らな版面と円筒状の圧胴の組み合わせで印圧をかけ、印刷する形式の印刷機。停止円筒型印刷機、2回転印刷機などがある。
円板式インキ練り装置
平圧式印刷機、とくにフート印刷機、手フートなどに用いられる簡易な着肉装置。
エンボシング
紙を雄型と雌型との間にはさみ、圧を加えて文字や絵柄を浮き出させること。
エンボス紙
凹凸模様が彫刻してあるエンボスロールにより、表面に凹凸加工を施した紙。
追い丁
分冊された書籍や雑誌の全巻にわたって、連続してつけた丁付け。
凹版
版面の凹んだ部分にインキを満たして印刷する版。凸版、平版と並ぶ基本的な3版式の一つである。
凹版印刷
版面の凹んだ部分にインキを満たして印刷する印刷方式。凸版印刷、平版印刷とともに基本的な印刷方式である。写真技術を利用した凹版印刷をグラビア印刷と言う。
凹版輪転印刷機
凹版印刷に用いる輪転印刷機。版胴に凹版版面が巻きつけられ、加圧機構を輪転式にしているため大量生産向きである。紙幣・切手・有価証券類の印刷に用いられる。
黄変
オーバープリントワニスや淡色インキの印刷面が経時と共に黄味に変色すること、ブリキ印刷の焼付け乾燥によって黄味に変色すること、紙自体が経時で変色することをいう。
オキシドライ装置
印刷物の裏移りを防止するために、印刷物表面に微細な粉を均一に散布する装置の一種。印刷物表面以外に粉が飛散しないよう粉を帯電させることが特徴。
奥付
書籍の巻末に、書名、定価、発行年月日、版数、著者名、発行者名、印刷者名などが印刷されている部分。
送り出しローラー
巻き取り紙を用いる輪転印刷機において、色見当や折見当のずれが起こらないよう、紙の張力を一定に保つために設けられる駆動ローラー装置。
OCR
光学文字認識と訳され、用紙上に印刷または印字された文字、記号を光学的に読み取り、コンピューターへ入力する装置。
OCRインキ
印刷文字を光学的に読み取る装置(OCRスキャナー)によってアナログ文字を直接デジタル変換し、コンピューターのデータ処理に用いる印刷文字用インキ。
オーバープリント
印刷の際に下地の色の上に、文字やロゴなどを刷り重ねることをいう。「のせ」ともいう。
オーバープリントワニス
印刷の最終インキとして印刷する無彩色、透明または半透明なワニスの総称。
オーバーレイ
ムラトリ法の一つ。印刷機の整備ができ、版をセットした後インキを供給、用紙を準備して印刷に移るが、活版印刷では特有のムラトリ作業が必要。
帯紙
書籍の表紙に巻いた帯状の印刷物をいい、一般に「帯」と呼ばれている。
オフセット印刷
版からインキ直接被印刷物に印刷しないで一度転写体に転移され、そのインキがさらに被印刷物に移される印刷方式。現在の平版印刷は特殊なものを除いて、このオフセット形式が主流。オフセットで名刺の印刷は当店では行っておりません。
オフセット印刷機
平版印刷機の一種で、版面のインキをブランケットと呼ぶゴムシートに一度移し、さらにブランケット上のインキを紙に転写する方式の印刷機。オフセット印刷機は弊社では封筒印刷専門で行っております。
オフセット校正機
オフセット印刷において、量産機での印刷前に試し印刷を行う機械。
オフセットダブリ
オフセット印刷機に特有のトラブルで、絵柄再現網点が少しずれて二重に重なって印刷される現象。
オフセット輪転
輪転式オフセット印刷機。通常、オフセット印刷は輪転式で行われるが、オフセット枚葉印刷には用いられず、オフセット輪転印刷機の略称として用いられることが多い。
オフセット輪転機
オフセット印刷機のうち、版を円筒状の胴にセットする方式の印刷機。シート紙を印刷する枚葉型と巻き取り紙を用いる巻取り型とがあるが、一般にオフセット輪転機という場合は巻き取り型をさすこごが多い。
オフ輪
オフセット輪転機の略称。
オペーク
ポジティブやネガティブの画像またはその周囲に塗布する遮光性のある塗料の総称。
表白
用紙の表面に印刷せず、裏面に印刷してあるページ。
表刷り
透明なフィルム素材の表側から印刷すること。裏刷りに対して使い分けをする。
表版
印刷するときに、用紙の表面に印刷する版。
およぎ
ネーム印刷のエッジが流れること、および平網印刷のムラを生じる現象。インキが低粘度の場合、被印刷体表面に油分浸透ムラがある場合に生じる。
折り
製本のさいに、印刷された紙(刷本)をページが正しい順になるように折りたたむ作業。
折り機
刷り本を自動的に折るための機械。その機能から、ナイフ式とバックル式、さらにこれを組み合わせた方式のものもある。
折り装置
印刷された用紙を所定の大きさに折る装置。輪転印刷機で印刷部から出てきた用紙をインラインで折り切断するものと、シート状の印刷物をオフラインで折るものとがある。
折丁
製本するために、刷り本を折ったもので、本の中身を構成する1単位。大きな一枚の紙に16ページ前後を一気に印刷し、それを折って本の形にしている。
オールサイズ輪転機
種々の寸法の紙に印刷が行える印刷機。枚葉印刷機では印刷流れ方向に種々の寸法の用紙が使用できる。
オンデマンド印刷
顧客が必要とする時に必要とする部数を印刷、製本し、在庫を持たないで供給する手法の一つ。オンデマンド印刷を効率よく達成するためには、原稿がデジタル化され、データベース化され、ダイレクト刷版による印刷またはデジタル印刷機により印刷され、電子的に丁合いされることが理想。弊社の名刺もこのオンデマンド印刷に該当します。
オンデマンドパブリッシング
文献などのデータベースから読者の要求項目を区分抽出整理し、提供する出版。
オンライン出版
インターネット上での電子雑誌のような、内容そのものをデータで供給しコンピュータ上からオンラインで購読する形態の出版。最近では自費出版として流行っている。
オンライン入稿
原稿を印刷会社に入稿するとき、原稿をデジタルデータの形で通信回線などを利用して行うこと。弊社でも名刺のイラストレータデータをオンラインで入稿して頂けるようになっております。
解像度
再現画像の分解可能なこまやかさの程度。
階調
原稿、ポジティブ、ネガティブなどのもつハイライトからシャドーまでの濃度の段階。
隠しノンブル
小口側でなくのど側に(見えないように)組まれたページ番号。
角背
上製本の様式の一つ。背を平らなまま仕上げたもの。角背に対し丸背がある。
加工紙
紙としての特性を生かしたままで、新たな特性を付与させるために塗工、含浸、貼り合せ、型付け、成形などの加工を行った紙。
重ね
巻き取り紙を用いる輪転印刷機の折装置やシートだし装置において、一定寸法に切断された印刷物を重ねて排出すること。印刷物の排紙形体の呼び方。
飾り罫線
罫線の中で複雑な模様をもつ罫線のこと。
画線太り
平版の画線部が製版または印刷のさいに太くなること。製版時では一般にネガフィルムからの焼付けにより画線部が太くなることが多い。
画像圧縮
画像の伝達や蓄積などを目的として、画像をできるだけ少ないデータ量で表現すること。
活字
活字組版に用いる方形柱状の字型。素材として鉛を主体とした合金、銅、木、合成樹脂などがある。
活字組版
活字、込め物、インテル、罫線などで組まれた凸版印刷用の版。線画凸版、網凸版なども含んでいう場合もある。
活版
活字を組み並べて作った印刷用の版。とくに小説などの文章物に多い。
活版インキ
凸版印刷に用いられるインキやオフセットインキと同様の組成より成る樹脂型インキと亜麻仁油をビヒクルとするアマニ油型インキがある。機上の温度上昇が激しいことから粘度変化が少なく、機上乾燥の遅いことが重要。
活版印刷
活字を組み並べて作った版で印刷すること。現在では活字を直に印刷するものと、その活字組版から複製した鉛版、樹脂版を使用するものとがある。
活版校正機
活版印刷用版の試し刷りを行う印刷機。平圧式と円圧式がある。
活版輪転機
版として、文字あるいは絵柄部が凸状のものを用い、凸部につけたインキを紙に転写する方式の印刷機のうち、円筒形の胴にセットした版と圧胴の間に紙を通し印刷するもの。
角切り機
主にシート状のカードを数枚積層し、四隅を平圧式で丸(角)型にて切りぬく機械。
角丸
書籍の小口の角を丸く仕上げる様式。辞書、バイブルなどに採用されている。
カートン原紙
厚手の紙にポリエチレンなどをラミネートした原紙。耐水性があるので牛乳、酒、ジュースなどの液体容器、あるいは紙カップなどに用いられる。
加熱転写印刷
剥離性の加工をした転写紙に図柄を逆刷りで印刷し、加熱、加圧することにより、被写体上に図柄を乾式転写する方法。図柄の印刷には種々の印刷方式が用いられる。
カバー
書籍の表紙の上に掛けられる厚手の紙のこと。その本のタイトルや絵柄を印刷したものが多い。
かぶり(印刷物の)
各印刷方式で使用する感光版材料の非画線部の汚れの現象。
被り(断裁の)
紙や本の中身を断裁する際に、切り口が湾曲すること。断裁枚数または部数が多いと下部の用紙または本に発生しやすい。
壁紙印刷
室内装飾として壁に張る紙に連続模様を印刷すること。印刷加工方法は壁紙の種類により異なる。一般紙に対しては、グラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷などにより印刷後、エンボス加工を行う。
可変データ印刷
1頁ごとに、あるいは1枚ごとに異なるデータ、すなわち「バリアブル・データ(可変データ)」を利用した印刷ができることを意味している。
カーボン印刷
複写を行う伝票などで、複写必要箇所にあらかじめカーボンを印刷しておく方法。一般的には用紙の裏側に印刷を行う。印刷方式としては凸版印刷方式とグラビア印刷方式があり、印刷のさい、インキを溶解して用紙に転位し、冷却固化する。
カーボン紙
紙の片面あるいは両面に、カーボンブラックなどの着色料と油またはろうなどの混合物を塗ったもの。筆記具またはタイプライターで複写をとるさいに用いる。
紙クロス
上製本表装材の表紙として丈夫な用紙が使用される。エンボス加工などをして布クロスに模した場合と、文字や絵柄を印刷する場合がある。
紙差し
シート紙を用いる印刷機に手で用紙を供給すること。現在の枚葉印刷機はフィーダーをもち自動供給するのが一般的である。
紙さばき
シート紙の自動給紙装置において、紙が複数枚重なって給紙されるのを防止するため、紙をセットする際に、紙が1枚1枚分離するように紙の隙間に空気を入れる作業。
紙揃え装置
印刷機の排紙装置から排出される紙を、往復運動をする平板で横方向から突いてそろえる装置。
紙積み台
シート紙の自動給紙装置にセットする紙をあらかじめ積み重ねるのに用いられる台。紙の端をそろえて積めるように台の側面に当て板が設けられている。
紙むけ
印刷時に紙面がむける現象。
ガム
オフセット印刷では不感脂化剤としてアラビアゴムが用いられるが、このアラビアゴムをオフセット版表面に塗布することによって、版表面を油分や傷などから保護する。
カラーカンプ
雑誌や広告の紙面をDTPやデザインシステムでデザインする際に、体裁を確認するためのカラー出力物。
カラーグラビア
カラー写真原稿を色分解し、分色ポジから赤、青、黄、墨の4本のシリンダーに製版し、4色を重ねた印刷。
ガラス印刷
ガラス板、ガラス容器などに行う印刷。印刷方法は主としてスクリーン印刷で直接または転写方式で行われる。
カラースキャナー
カラー原稿を走査して変倍、色修正、階調修正を行い分解版を作成するためのスキャナー。
カラーチャート
種々の網点面積率をもつ黄、マゼンタ、シアン、墨の各色を、標準用紙と標準インキで刷り重ねた色票を系統的に配列した表。各版の網点面積率より印刷物の仕上がりを予測したり、逆に希望する色に対して、各色の必要な網点面積率を知ることができる。
カラーデュープ
カラーフィルムをもとに撮影や焼付けにより画像を複製すること。
空通し
枚葉印刷機で行う方法で、ブランケット胴を入れずに紙を通すこと。胴刷りしたインキの除去、パウダーの除去、用紙に紙癖がある場合に行う。
カラートーン
透明フィルムに着色または色網10~70%を印刷したシート状のもので、接着剤が塗布してある。必要な形状をカッターで切り取り、デザインワークに利用する。
カラーパッチ
黄、マゼンタ、シアンなどに色票を印刷した色紙で、色分解のさい、原稿のわきに添えて撮影する。
カラーバランス
多色印刷において、使用される写真原稿の色材料の発色バランス、および印刷インキの発色バランスをいう。
カラープルーフ
製版でフィルム作成後、クライアントへチェック用に提出する色校正刷りのことをいう。
感圧紙
感圧複写紙。筆記具によって複写をとる加工紙。狭義にはノーカーボン紙をいうが、広義には裏カーボン紙をも含める。
簡易校正
実際のインキ、紙、印刷機を使用せずに、印刷見本を作る方法および印刷見本。狭義には、階調性、色調、シャープネスなどが印刷物に近似するもの。
間紙
印刷インキが乾かないうちに次の紙が重なると、インキが裏移りする。これを防ぐために印刷紙1枚ごとに挿入する紙。最近の印刷機では間紙を使うことはまれ。
環境対応型インキ
低臭気等の作業環境の改善や大気汚染が少ない、生分解性等の地球環境・エコロジーに対応するよう印刷インキの成分を調整した商品。
観音折り
印刷された用紙を平行に四つに折り、両端を扉状に内側に折り返した折り方式の一種。
カンプ
デザイナーが広告やカタログをデザインした結果を出力したもの。
機械校正
活版印刷において、ムラトリ前の試刷りで行う校正。
キャストコート紙
厚紙に塗料を塗り、塗工層が水分を含み可塑性を有する間に、鏡面を有するクロムメッキドラムに塗工層を押し当てて乾燥したのち、剥離して鏡面を写しとり強光沢としたコーテッドペーパー。
キャリブレーション
スキャナーの操作パネル上のメーター値を実際の出力値に合わせる操作。
給紙機
印刷機の印刷装置に用紙を送り込む装置。
給紙胴
枚葉印刷機の給紙部にあり、前当て、横針で制止した紙を高速で回転している圧胴へ受け渡すための胴。
給紙ブレーキ
巻取印刷機の給紙部にあり、紙に適度な張力を印刷中に与えるブレーキ装置。
吸塵装置
巻取印刷機で、用紙に付着している紙粉やごみを取り除くために供給部に取り付けられた装置。
吸油度
紙が印刷インキなどを吸収する程度。
共通圧胴型印刷機
フレキソ印刷機の一種で、大きな共通圧胴の周囲に印刷ユニットを配置し、被印刷体は圧胴に抱かせて走行し印刷する機械。センタードラム型印刷機、コモンインプレッション型印刷機ともいわれる。
経本折り
経本の折り方。アコーディオン状に折った刷り本を丁合いし、小口部分を接着剤で固定して仕上げる。
曲面印刷
三次元立体曲面をもつ製品の表面に行う印刷。被印刷体の種類、用途により、凸版印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷、タコ印刷などが用いられる。
清刷
活字組版およびその他の凸版原版から良質の紙に鮮明に刷った印刷物。
キーレスインキングシステム
紙幅方向のインキ供給量調整キーをなくしたインキ供給システム。
金属印刷
金属表面に行う印刷。おもにオフセット印刷で行われているが、スクリーン印刷、熱転写印刷法なども用いられる。
金属箔紙
上質紙、純白ロール、クラフト紙などと金属箔とを接着剤などを用いて貼り合わせた加工紙。
金箔
金を箔状にしたもので、製本では金付け、箔押しなどに用いられる。
クイックオフセットインキ
枚葉オフセット印刷において、表面を印刷した後すぐ裏面が印刷できるか、すぐ加工に入れるようにセットを速くしたインキ。
くせ取り棒
巻取印刷機で印刷装置に用紙が入る前に、用紙のしわ、あるいはくせなどを取り除くための棒。
口絵
書籍や雑誌などの巻頭に載せる絵や写真のこと。
口糊
表紙と見返しとを接着させる方法の一種。小口側の一部にのりを塗布して見返しと表紙とを接着させる。
グラシンペーパー
化学パルプを長時間粘状叩解し、抄造後、加湿し、強圧でスーパーカレンダー掛けをした透明感のある薄紙。
グラビア
凹版印刷のうち写真技術を応用し製版を行った凹版での印刷。
グラビアインキ
グラビア印刷に用いる溶剤蒸発乾燥型インキ。
グラビア印刷機
印刷3方式の一つ。凹版のうちのグラビア版胴を備えた印刷機。
グラビアオフセット印刷機
一般のグラビア印刷機は版胴から直に紙へインキ転写させるのに対し、版胴からいったんブランケット胴にインキを転写さ、それを印刷する印刷機。
グラビア輪転機
巻取り紙を印刷するグラビア印刷機。高速多色印刷ができ、能率が高い。
グリーシング
オフセット印刷における地汚れの一種。
クリスタリゼーション
多色印刷において、下刷インキの乾燥後に上刷インキを印刷しようとするとき、上刷インキが下刷インキにはじかれてトラッピングしないか、容易に剥離する現象。
グリッパー
枚葉印刷機で用紙を搬送するために圧胴、中間胴、排紙部にある紙をくわえる爪。
グル
造本時、本文の一部または表紙を間違って天地・小口方向を逆に製本すること。乱丁本、落丁本と並ぶ不良本の一種。
くるみ
製本工程のなかで、表紙を中身に取り付ける作業。
くるみ表紙
一枚の表紙材料で中身をくるみ、三方を仕上げ断裁する仮製本様式の一つ。
クレータ
グラビア印刷において印刷面に凹凸が発生して噴火口状に見える現象。
グレーバランス
通常、印刷に使われる3原色インキは理想的な光吸収をしないため、無彩色グレーを得るためには3色の量を加減する必要があり、この量関係をいう。
グロス
印刷面の光沢を示す。
グロスインキ
普通に用いるインキよりも光沢を重視したインキ。
くわえしろ
枚葉紙でグリッパーがくわえるために必要な紙幅。寸法は印刷機によって異なるが、10mm前後が一般的。この部分には印刷はできない。
罫
線を印刷するために使われる金属製の薄板。
軽印刷
一般印刷と比較して、比較的簡単な設備で小部数のものを迅速に製版印刷する方式。版材の対刷力から考えて1,000部以下が対象で、多色印刷は軽印刷に含まれないのが一般的。軽印刷では最もスピードが優先され、発注から納期までの期間が短く、一般印刷に比して品質は第二義的。
軽量コート紙
塗工量が5g/平方メートル程度の塗工印刷用紙。主にオフセット印刷、グラビア印刷の雑誌本文、ちらしに用いられる。
化粧裁ち
印刷物や本の中身を仕上げ寸法どおりに正確に断裁すること。
化粧板印刷
天然の美しい木目その他の模様の金属板、合板などへの印刷。
ケツ
凸版印刷において発生する不良の一種。版の空白部が汚れて印刷されてしまうこと。
毛抜き合わせ
製版用語。異なる印刷絵柄を並置デザイン指定する場合に、髪の毛一本の隙間もなく見当合わせをすること。
下版
校了になった組版を、清刷、紙型取り、印刷などの次工程へ移すこと。
ゲラ刷り
元は活版組版の用語で、組版してゲラに入れたものを、ゲラごと校正印刷機にのせて刷った「校正刷り」のこと。
減感インキ
感圧複写紙の発色不要部にスポット印刷をして発色作用を抑える目的に用いるインキ。
減感印刷
複写を行う伝票などで、化学的反応を利用したインキをコーティング加工した用紙を用いる場合に、発色させたくない部分に反応抑制剤を印刷する方法。
原色版
活版の多色版。カラー原稿を色分解して4色ネガを作り、それらより写真凸版を製版したもの。
原色版インキ
網凸版方式の印刷に用いるプロセスインキ。
見当
多色印刷における重ね合わせの位置精度、単色印刷における表面と裏面の位置精度、用紙を折るときの折位置精度、印刷絵柄に合わせて打ち抜くときの位置精度。枚葉印刷では位置精度を出すために横方向は針と呼ばれる断裁面へのアテを使用し、流れ方向に対しては前アテと呼ばれるものを断裁面に当てて、印刷胴と同期させて紙を送る。
見当合わせ
多色印刷においては各色版の刷り込み位置合わせ、単色印刷においては表裏の用紙刷り込み位置合わせを行うことをいう。
ケント紙
おもに製図用に使われる画用紙で、イギリスのケント地方で作られたもの。
合紙
2枚以上の紙を貼り合せる加工。通常、印刷した紙を板紙と貼り合わせて、厚みや強度をもたせるために行う。
校正
印刷物を印刷する前の段階で、校正刷の誤りや体裁上の不備などを原稿と照らしあわせて訂正すること。
校正機
校正刷を印刷するために印刷機を簡単な構造にした機械。
校正記号
印刷物を校正するときに用いる記号。
高精細印刷
175線あるいは200線商用スクリーン線数より高いスクリーン線数での印刷。一般には500線以上の印刷物をいう。
合成紙
合成樹脂のフィルムを主成分とし、天然の紙に似た外観、風合いをもち、合成樹脂の特性を残しているものの総称。
合成紙用インキ
天然のパルプ紙に対し、合成樹脂ベースの合成紙の印刷に用いるインキ。
校正刷
校正を行うために仮に刷った印刷物。
合成繊維紙
合成樹脂の繊維を主体に天然パルプを一部加え、天然パルプと同様に抄造されてできる紙状薄葉物。
校正用インキ
校正ー本刷間では印刷条件の違いから網点の太りがことなる。本刷りの方が網点が太りやすく、盛りも少ないことから、あらかじめ本刷に近似させるよう、濃度を低く、タックも低く設定したインキを用いる。
高濃度印刷
通常使用する印刷インキより20~30%程度濃度を高めたインキを使用した印刷。通常の印刷インキよりも色再現領域を広くすることが期待できる。
孔版
画線部が貫通孔、非画線部がインキを通さない膜により形成された版を用い、版の裏面からインキを押し出し、通過したインキを紙やフィルムなどの被印刷体に刷り移す印刷方式の総称。謄写印刷、スクリーン印刷、タイプ孔版などがこれに属する。
高品位印刷
色分解、インキ濃度、網点の大きさ等に工夫して従来の印刷品質より高い再現性を得る方式。
校了
校正が完了すること。校正者や編集者または著者によって校正された校正刷は印刷会社に戻され記入された赤字の指示にしたがって差し換えなどの訂正が行われる。再校、三校を重ねて校了となるが、印刷して差し支えない状態によれば、校了とし朱書きするか「校了」の押印をする。一部印刷会社の責任において訂正する箇所があれば責任校了として印刷会社にもどす。
校了紙
校正を完了して、印刷可能な状態の校正紙。
小口印刷
小口装飾の一種で、本の小口にゴム凸版、パッド印刷などにより印刷をすること。辞書の小口面の見出しの五十音やアルファベットの印刷に用いられる。
故紙
印刷工程上で生じる使用済みの用紙や、製本工程上の断裁片、あるいは不要となった新聞・雑誌・帳票類などの総称。
腰帯
本の表紙またはカバーの上に巻かれる帯状の印刷物。
ゴースト
印刷版絵柄にない濃淡が印刷時に生じるトラブル現象。印刷インキングの供給量と需要量が、隣合わせる絵柄によって対比的な場合により生じる。またインキ着けローラーおよび練りローラーの圧力が足りないか高すぎる場合、インキが版面に供給されず、印刷胴とインキ着けローラーの径が異なる場合、ローラー目として生じる現象をいう。トブづけの印刷機では生ぜず、インキングローラーを用いる印刷機すべてに生じる。印刷絵柄で印刷流れ方向に対し、半分が絵柄で半分が矩形の場合の境界線上で絵柄に濃淡が生じる現象。
こすれ
印刷面が印刷機上、折機、製本丁合、物流でこすれて汚れおよび傷がつく現象。一般印刷ではワックスをインキに混合し、インキ表面が滑るようにして、こすれを防止する。また印刷機上、製本機上では、インキが一度搬送系によりこすられると堆積して、すぐに激しく傷が発生する。印刷物をワックスで滑るようにした場合、物流での刷本間移動が激しくなり、物流こすれを生じる危険性がある。枚葉オフセット印刷では、インキに合成樹脂ワニスまたはコバルトドライヤーを加え、かたい皮膜をつくり救済する。
コットンペーパー
軽くて弾力性にとみ、かさ高で光沢のない書籍用紙。
コート紙
アート紙よりも塗工量が少ないコーテッドペーパー。
ゴバン目テスト
クロスカット試験ともいう。塗膜やインキ皮膜の基材への接着力の試験法。
ゴム胴
オフセット印刷は版胴のインキを、これに接して回転する胴に転移させた後、紙へ印刷する。これをゴム胴とよび、ゴムブランケットを巻きつけている。
ゴム版
フレキソ印刷に用いられる刷版。版材として、天然ゴム、合成ゴムが用いられ、刷版手法から、鋳造ゴム版、手彫りゴム版がある。
ゴム版印刷機
ゴム凸版を用いて端物印刷を行う活版印刷機。
ゴム引き
平版の刷版および印刷時に、版面の感脂防止、保護などの目的で版面にアラビアゴムまたはこれに酸などを加えたエッチング液を塗布すること。
ゴムブランケット
ゴム層と布の層を3~4重層交互に重ね合わせて作ったもので、表面がゴム層から成っている。
ゴムローラー
ゴム製の印刷インキローラー。耐インキ性の合成ゴムがふつう用いられる。
コロタイプ
平版印刷法の一種で、写真製版で行う最も古いもの。
コロタイプインキ
ゼラチンをアルミや硝子基材に塗って版とするコロタイプ印刷に用いる酸化重合乾燥型平版インキ。
コロタイプ印刷機
コロタイプを印刷する機械。コロタイプは平版の一種で、ゼラチンを用い、表面に微細なちりめん状のしわができることを利用した印刷法で、調子再現性に優れ、美術品の複製、写真印画などの高級な印刷に用いられる。
コンタクトスクリン
連続調フィルム・印画紙から、写真製版用網ネガまたは網ポジを得るときに用いる製版用スクリン。
こんにゃく版
にかわとグリセリンとを混合したゼリー状の平版。
コンパウンド
印刷適性、印刷品質、後加工性などを改善する目的でインキに混合するペースト状添加剤の総称。
コンビネーションプレス
印刷機に加工装置を連結し、インラインにした機械。
再校
初校戻しの赤字を直した2度目の校正あるいは校正刷。
再生紙
明確な定義はなく、グリーン購入法では、古紙配合率が70~100%の情報・印刷用紙、白色度が70%程度の非塗工紙としている。
再版
書籍の出版で初版の発行後同一版で再び出版すること。正しくは再び製版し直して印刷、出版する場合をさす。
作字
2本または3本の活字の不用部分を削って、必要部分を組み合わせて特殊な漢字を作る作業、またはその合成活字。
差し替え
校正の訂正指定に従って、組版中の活字、込め物、インテル、罫線などを差し替えて、版の訂正を行うこと。
差込印刷
文書の一部に他のファイルのデータ、例えば文書の内容は変えずに、宛名を差し換えながら印刷をすること。
刷版
実際に印刷機に取り付けて印刷するための版。
刷了
全部の用紙を刷り終え、印刷機から版をはずしても支障のない状態のこと。
サテライト型オフセット輪転機
巻き取り紙を用いて、輪転式で平版オフセット印刷する機械をオフセット輪転機という。この中で1本の太い共通圧胴の周りに数組の版胴とゴム胴とを配置したものをサテライト型と呼ぶ。
更紙
化学パルプ40%未満配合の非塗工印刷用紙。下級印刷用紙として、雑誌本文や謄写版印刷などに使用される。
ざらつき
印刷物網点の再現が不完全であり、網点が素抜ける場合をさす。
三三判
規格外原紙寸法の一つ。697×1000mmをいう。
三四判
規格外原紙寸法の一つ。727×1000mmをいう。
3色版
絵画、写真、実体などを原稿とし、色彩を表すのにもっとも便利な、イエロー、マゼンタ、シアンの版を作り、それぞれ適応する色インキを着けて順次刷り重ねて印刷する方法。
三方断裁機
本の天地、小口、すなわち三方を1回の操作で連続的に仕上げ裁ちできる高能率な断裁機。
ザンメル印刷
一つの版に部分的に異なる色のインキをつけ、一度に多色刷りを行う特殊印刷法。
仕上がり寸法
実際に本、チラシ、カレンダーなどになるときの大きさで、断裁機にて裁つ際、目印となる裁ちトンボの内側の大きさ。
紫外線硬化型インキ
高エネルギー電磁波の一種である紫外線を照射することで硬化するインキ。
直刷り
オフセット印刷に対して、版から被印刷体に直接印刷する方式をいう。
直刷り平版インキ
オフセット印刷に使用する版材を用い、版からブランケットを介さず、直接紙に印刷する直刷り平版用のインキ。
磁気印刷
磁性インキを用いて、文字や記号、ストライプを印刷すること。文字や記号の磁気印刷は容易に目視にて判読できる点と機械的に読み取りができるという利点がある。
色差
色の相違を数量的に表したもの。
ジグザグ折機
連続伝票において印刷機排出部で折丁やシートの形をとらず、ジグザグの経本状に連続して折るための折機。
シーズニング
抄造後の用紙を一定の温度・湿度中に放置し、用紙含有水分量を安定させること。
試刷
印刷機で本番印刷に入る前に試しに印刷すること。
下固め
製本での本固め前に仮に本文の背を一冊づつ接着剤で背固めする作業。
字面
文字面のことで、印刷の際にインキが付着する部分をいう。
質感
印刷再現を表現するのに、色彩、量感と並列して用いられる慣用句。
湿紙機
印刷前の用紙を加湿する機械。水を噴霧器でスプレーし、その中へ紙を連続的に送って加湿する。証券などの凹版印刷のさいに、印刷を容易にするために用いられる。
辞典用紙
辞典、薬品説明書などに使用される印刷用紙。
自動紙継ぎ装置
巻取紙印刷機において、印刷している巻取り紙が終わる時、印刷機を停止させずに次の巻取り紙へ自動的に紙を継ぐ装置。
自動給紙機
枚葉印刷機、枚葉折機などで、棒積みした紙を自動的に1枚ずつ供給する装置。
自動現像機
露光後のフィルムなどを感光材料を自動搬送し、現像・定着・水洗・乾燥する機械。
自動見当合わせ装置
輪転印刷機において、多色印刷の色合わせ、断裁長さ、折などを自動的に制御する装置。
紙粉
紙面に付着した粉末状のごみ。印刷時にこのごみが版面やブランケットに付着したり、インキつぼに混入すると、印刷部分が白点状にぬけるヒッキーの原因となる。
湿し装置
オフセット印刷機の版面に湿し水を供給する装置。
湿し水
平版印刷の非画線部にインキが付着しないように版面を湿らせる水。
湿し水循環装置
オフセット印刷の湿し水を供給するために、印刷機の外部に設けたタンクからポンプによって連続的に水舟に水を送り、水舟からオーバーフローした水をタンクにもどして循環させる装置。
湿しローラー
オフセット印刷で、版面上にインキを反発する湿し水を運ぶローラー。
地紋
主要な絵柄の背景に刷る淡色の網点、砂目、彩紋などの模様。
写植
写真植字を略して写植という。写真植字機を使って印刷用文字を作成する方法。
写植機
写真植字機を略して写植機という。
写真植字
略して写植ともいわれ、写真植字機を使って印刷用の文字や記号、罫、パターンなどを作成する技法。
写真植字機
写真的に文字を印字し、製版用文字版下を作る機械。
シャープネス
印刷の鮮鋭度。印刷ではインキを使用するため、エッジの再現が原稿より劣りやすく、これを防止するために、製版の色分解機においてエッジに濃淡のレリーフを電子的につける。
集版
カメラまたはスキャナー工程で作成された線画ネガや色分解ネガなどをライトテーブル上で指定に従ってまとめ、1枚の印版焼付け用のフィルムに仕上げること。
樹脂グラビア版
グラビア印刷用版材の表面に樹脂を使用したもの。
出校
印刷会社が、作成した校正刷を発注者に校正のために送ること。
出張校正
校正者や編集者または著者などが印刷会社へ出向いて校正を行うこと。
出版グラビアインキ
週刊誌、月刊誌などの雑誌類の表紙や写真ページに用いられるグラビア印刷用インキ。カラー印刷用に使われるものが多い。
出力機
入力機およびコンピュータからの画像・文字やレイアウトを紙や製版フィルムに出力する装置。
昇華型転写捺染印刷
加熱することにより昇華性を有する染料をインキとし、絵柄を転写紙にグラビア印刷方式で印刷した後、転写原紙を布に重ねて加圧加熱して、原紙の絵柄を布に転写する染色法。
証券印刷
紙幣、株券、債券、預金通帳、商品券などの印刷。
上更紙
化学パルプ40%以上、70%未満配合の非塗工印刷用紙。
上質紙
化学パルプ100%配合の非塗工印刷用紙。印刷用紙の代表的品種であり、書籍、教科書、商業印刷などに使用される。
蒸発乾燥
印刷後に溶剤が急速に蒸発することによって、被印刷面に樹脂分や顔料分が残って固着するもので、乾燥速度はきわめて速いため、高速・多量印刷に適している。
植字
活字、込め物、インテル、罫線などを組み合わせてページ単位の版を作る作業。
初校
組版した最初の校正あるいは校正刷。
書籍用紙
書籍の印刷に適した、地合いが均一で、不透明度の高い用紙。
書籍輪転機
書籍、雑誌の活版ページを印刷する凸版輪転印刷機。
ショートラン印刷
一般にいわれている「小ロット印刷」のことをいう。小ロット印刷の数量の定義は明確ではない。
ショック目
オフセット印刷物で、シリンダー軸方向に平行に帯状の印刷濃度ムラが発生すること。
シール印刷機
印刷、浮き出し、打ち抜きをインラインで行って、シールやラベルを製造する機械。
シルクスクリーン印刷
スクリーン印刷に同じ。
白板紙
板紙の一種で、印刷適正や製函適正がよいことを特徴とする。
白抜き
文字、模様などの原図の黒部を白部とする方法で製版、印刷の状態をいう。
新聞印刷
新聞を製作する技術および方法。新聞としての機能を果たすため、短時間で大量の印刷を行うことが要求される。
新聞輪転機
新聞を印刷するための巻き取り紙輪転機。
水性インキ
水溶性樹脂またはアミンやアルカリで水溶液とした樹脂を水やアルコールに溶解させたワニスを用いるインキ。印刷物の臭気が少ないので食品包装用インキとして、グラビア印刷、フレキソ印刷で使われることがおおい。
スカッフィング
印刷物の後加工の工程または輸送上などにおいて、摩擦によってインキがこすり取られること。
すき込み
紙の厚さの変化により、紙を透かしたさいに現れる模様、またはそのように加工すること。
スキニング
酸化重合型オフセットインキに一般的に見られる現象で、インキ表面に乾燥膜ができること。印刷機の長時間停止時や保管時間によって発生する。
スクリーン印刷
孔版印刷の一種。枠に紗を張り、画線部以外の部分の目を樹脂などでつぶしたスクリーン版を用いて、版の紗面からスクィージの擢動によってインキを押し出し印刷する方法。
スクリーン印刷機
スクリーン印刷を行う印刷機。平面用と曲面用があり、平面用では紙、プラスチック、プリント配線基板などの印刷が行われ、曲面用はびん、コップなどに印刷される。
スクリーン角度
網撮りまたはスキャナーによる直網分解のさい、スクリーン線もしくは出力網点が垂線となす角度。
スクリーン線数
スクリーンの単位長当たりの線や点の数。これにより製版用スクリーンの目の精粗を示す。
スクリーントーン
透明なフィルムに網点・万線などの模様を印刷し、裏に接着剤が塗布されたもの。
スケルトンブラック
多色印刷用に用いられる墨版の一種。ハイライトから中間調にかけてほとんど調子がなく、中間調からシャドー部にかけて強いコントラスト階調をもつ。
筋押し
厚手の切りつけ表紙を開きやすくするため、折り曲げ部分に筋を入れる作業。
スタッカー
輪転印刷機の折機などから排出される折丁の員数、揃え、積重ねを自動で行う装置。
スタック型印刷機
独立した圧胴を備えた印刷ユニットを積み上げるように配置したフレキソ印刷機。ごく標準的な形式で紙の印刷に用いられる。
ステンシル印刷
シルクスクリーン印刷、セリグラフとともに、孔版印刷の一種。
スナップアウト帳票
封筒の周囲を切り取らずに中紙を簡単に取ることができる帳票。
すの子
印刷直後のまだ乾燥していない印刷物を、少量ずつ取り分けておくための板、または箱。
スノーフレーク
オフセット印刷物のベタ部が滑らかにインキの転移しない雪片状の模様の出る状態。
スペクタカラー
あらかじめグラビア輪転機などでカラー印刷された巻取り紙に、あとからニュース性のある記事を見当を正しく合わせて印刷する新聞印刷の方法。
スペックル
グラビア印刷において、グラビア版セルよりインキが転移せず、印刷物に白い斑点を生じるトラブル現象。
スポットカラー
新聞印刷において、大きな見出しや広告のために部分的に単色カラー印刷を行うこと。
刷足し
印刷を終了した印刷物に色不良や員数不足をした場合などに、これを補足するために印刷すること。
スリッター
巻取り紙輪転機や紙加工機などにおいて、紙を流れの方向に切る装置。
刷本
製本では、中身になる印刷物で、折りたたむ前の状態のもの。印刷においては、刷り上った印刷物の総称。
刷目打ち
印刷機を用いて刷本に切り取り用の線状の小さな穴をあけること。凸版印刷では、版面に穴あけ用の線を組み付けて印刷と同時に穴あけをする。
背
書籍のとじ側。小口の反対側をさす。とくに上製本では、背の形により丸背と角背に分類される。
静電印刷
印刷において、インキの転写を静電引力を利用して行う方式で、物理的圧力を必要としないため曲面への印刷、強度の低い被印刷物への印刷が行える。一般に印刷版は導電性のスクリーン版を用い、被印刷物を介して対向電極間に電圧を印加し、スクリーン版上に供給したトナーインキを被印刷物に転写させる。
静電グラビア印刷
グラビア印刷でインキの転移性を改善するため、アメリカのGRIで開発された方法で、印刷紙の後面から電圧をかけ、静電引力によりインキ・セル上のグラビア・インキを盛り上げ、インキ転移性を向上させるもの。
静電スクリーン印刷
スクリーン印刷で液体インキの代わりに乾燥した粉末トナーを用い、静電気の吸引力を利用して基材へ印刷することをいう。
製版指定
印刷原版を作成するために必要な設計指示。
背固め
製本でのくるみ工程前に本文の背を背紙などで補強する作業。
責任校正
著者または発注者から任されて印刷会社側で行う校正。
責任校了
直し箇所が少ない場合など、印刷会社が責任をもって校了とすることを前提として、注文者が校了すること。
石版印刷
石版石を版材とする平版印刷の一つ。
石版印刷機
石版印刷を行う印刷機。手動印刷機と停止円筒印刷機の形式がある。転写方式には直接印刷とオフセット印刷の2方式がある。
背丁
各折丁の順番を簡単に見分けるために、折丁の背の部分に刷り込んだ記号。
セットオフ
凸版輪転、オフセットインキの品質事故の一つで、印刷面のインキのセット、乾燥が遅いため、印刷物を重ねたとき対向面を汚す現象。
セパレーションネガ
写真原稿などを光学系の処理により、印刷に必要な4色の成分に分け、露光されたネガフィルム。
背標
各折丁の背の部分に印刷する目印。
全紙掛け
印刷用紙の寸法が正寸の大きさのまま、版を組み付けて印刷する方法。
線数メーター
網がけされた印刷物のスクリーン線数を読み取るためのパターンの付いたフィルム。
センタートンボ
トンボにはいろいろな種類があるが、製版や印刷工程における印刷物の天地・左右の中央の位置を示すトンボをいう。
全判
枚葉印刷紙の断裁する前の基準となるサイズ。
先方紙
印刷会社が印刷物を受注するとき、出版社などの発注者が印刷用紙を支給することを、先方紙という。印刷会社から見て先方を意味している。反対に印刷会社側が購入して準備する用紙を、当方紙という。
ソアリング
グラビア印刷やフレキソ印刷でインキパンの中に空気中の水分が凝縮して、インキ中に混入すること。
装丁
表装材をはじめ表紙のデザイン、外箱、カバー、見返し、扉などに種々の意匠を加え、本の体裁を美しく装うこと。
総ルビ
和文の組版で、すべての漢字にふりがなをつける組み方。一部の漢字のみふりがなをつけるパラルビに対していう。
損紙
印刷中、種々の要因により発生する実用に供しない用紙のことで、印刷した損紙を黒損、印刷前の白紙の損紙を白損という。
耐刷力
一つの版で印刷できる限界の通し枚数のこと。一般に印刷物の品質が明らかに低下し始めたときをもって、その版の寿命が尽きたとする。
退色
印刷物、紙などの色が変色し薄くなる現象。
ダイリソ印刷
新聞印刷に用いられる平版直刷方式の一種。
ダイレクト印刷
版を作成せずに印刷を行う方式、およびこの方式を利用した印刷システム。
ダイレクト刷版
フィルム原版を作成せずに刷版を作成する方式、およびこの方式を利用した刷版システム。
台割
ページ物印刷をするとき、印刷機1台によって一度に印刷されるページ数に、総ページ数を分割すること。
高台印刷機
平台印刷機の停止円筒型で、紙を圧胴の上側から供給し、フィーダーボードの下に排出方式。ドイツの印刷機に多い。
タコ印刷
インキ盛りをした凹版版面にゼラチンやゴムなどの球状弾性体を圧着して、弾性体表面にインキを転移させ、それから被印刷体に圧着して印刷する方式。
タコ印刷機
曲面に印刷する機械。凹版を用い、にかわとグリセリンでできたたこの頭状の弾性体にインキを移し、被印刷体に転写することからこの名がついた。
多色印刷
製版方法や印刷方法に関係なく、2色以上のインキを使って刷り重ねる印刷の総称を「多色印刷」という。
多色凹版輪転印刷機
紙幣、株券などの金券に凹版で多色を同時に印刷する枚用印刷機。
多色オフセット印刷機
多色刷を行うオフセット印刷機。
多色グラビア輪転機
多色刷を行うグラビア印刷機。グラビアの印刷ユニットを色数分つなげて構成される。出版用では表4色、裏4色の88色が一般的で、建材等の特殊印刷では3~8色。
多色凸版輪転機
多色刷を行う凸版印刷機。枚葉紙と巻取り紙用がある。出版用にはほとんどなく、ラベルなどの特殊印刷に用いられる。
裁ち落とし
本の三方などの四方を裁つこと。
裁割り
枚葉印刷機で印刷する用紙サイズは、倍判または全判など多面付けが一般的。一方、折機で折る場合は一面全判または半裁以下なので、印刷用紙をあらかじめ必要サイズに断裁する必要があり、その断裁作業を断割りという。
タックバランス
オフセット多色印刷において、ウェット印刷する場合、刷り順によってタックを変化させることにより、重ね刷りが容易になる。一般的には先刷インキのタックは高く、後刷インキにしたがって低い。しかしながら、使われる用紙、印刷スピード、印刷室温度、インキ量、画線部の面積、インキの湿し水特性などによって変わることがある。
ダブリ
同一版の印刷画線が二重三重にずれて印刷される現象。ダブリには単色印刷で起こる単色ダブリ、多色印刷時に起こるオフセットダブリがある。
ダブルエンダー
ドラム型印刷機において、1ドラムで表裏同時印刷するための装置。
ダブルトーン
写真原稿を角度を変えて2枚のネガを撮り、2種のインキで刷り重ねたもので、グラデーションの豊富な印刷物になる。
タブロイド判
新聞判型の一種。通常の新聞判型の半分程度の小型のものをいう。
ダミー
見本本のこと。本の出版企画にあたり、製品見本として本文、表紙印刷すべてを行い作製された本。
多面焼付け
1枚のフィルム原版から版材に繰り返し焼き付けて、同一面に同一の絵柄のある多面の版を作ること。
ダルアート紙
塗工紙の艶消し仕上げの一つ。印刷された部分のみ冴えた光沢が得られ、印刷されてない白紙面は半光沢のダル調の仕上がりになる。
断裁機
積み重ねた紙を所要の寸法に断ち切る機械。その種類は、おもに裁割りや材料、付属印刷物の裁断に使用される平断裁機と仕上げ断裁に用いられる三方断裁機とに分かれる。
タンデム型
印刷機や印刷後加工機などにおいて、同型の印刷、加工ユニットを縦型に連結した型。
単胴型
多色印機の構造の一つ。1本の大径圧胴の周りに多色印刷版胴がこれを囲むように取り付けられているので、巻き取り紙はこの周りを1回転することにより多色刷ができる。弱いテンションでの印刷が可能。
ターンバー
巻取り紙印刷機で、紙の流れ方向を変えるためのローラー状の棒。
ダンプニング装置
オフセット印刷機において、版に湿し水を供給する装置。
段ボール印刷機
初期の段ボール印刷は、油性インキを用いた凸版印刷で行われていたが、近年は乾燥の速いフレキソ印刷が採用されている。
地
本の中身を仕上げた寸法に断裁した際、本の三方の切り口のうち、下部の部分。上を天、綴じ側と反対の切り口を小口というが、天・地・小口を総称して小口という場合もある。
チェーンデリバリ
枚葉印刷機の排紙装置の一つ。最終ユニットを出た枚葉紙は、横一列にくわえ爪を取り付けた棒でくわえられ、チェーンで印刷機の紙積み台まで運ばれる。
千鳥掛け
全部片面だけが印刷されて裏白となるような版面の掛け方。配列は本掛けと同じ。印刷されない白のページの部分に空版を置く。
着肉ローラー
印刷機の版にインキを与えるローラー。インキはインキ壺より、呼び出しローラー、練りローラーを経て練りならされたのち、着肉ローラーより版面に供給される。
中間胴
ユニット型枚葉多色オフセット印刷機において、前の印刷ユニットの圧胴から渡し爪を介して印刷紙を受け取り、次の印刷ユニットの圧胴に渡すための胴。
中質紙
化学パルプが70%以上で、残りは、砕木パルプである印刷用紙。
チューブ印刷
金属チューブ、プラスチックチューブ、ラミネートチューブへの印刷の総称。
丁合い
折丁をページ順にそろえ、1冊分ずつまとめる作業。手作業で行うのが手丁合い、丁合い機で行うのを機械丁合いという。
丁合い機
自動的に丁合いを行う製本機械。
超光沢ワニス
オフセットインキに使われる原料ワニス、通常のワニスよりも光沢のよいワニスをいう。
調湿紙
紙の水分含有量をあらかじめ定めた湿度に調和させた紙。この処理を調湿といい、印刷機上の寸法安定性をよくする目的で行う。
チョーキング
印刷後、インキ中のビヒクル成分が紙に吸収され顔料分だけが紙表面に残るため、指でこすると容易にとれてしまう現象。
チルロール
高温で乾燥されたオフセット輪転印刷インキの冷却やポリエチレン押出しラミネート直後の冷却に使用されるロール。
束
本の中身の厚さ。本文用紙・装丁材などの種類が決まると、これを用いて白紙のまま数冊試作し、これを束見本という。
束見本
印刷物を製本する際、中身の厚みを確認するために、本文用紙・装丁材を用いて試作する見本。
突揃え機
刷本の針側およびくわえ側を自動的に揃える機械で、裁割りの前に使用される。
突き針
枚葉印刷機の印刷ユニットに入る前に紙の位置を規制する針状のガイド。
付物
書籍の本文に対して、前付、後付、別丁など、本文を除いたものの総称。また出版物に付属する印刷物の総称。売り上げカード、腰帯、カバー、ケース、ブックジャケット、愛読者カード、など。
付合せ
別の印刷面を同一の版に焼き付けることをいう。たとえば、ある雑誌の表紙とほかの雑誌の表紙を同一版に焼付け、印刷することを「掛け合わせ」ともいう。
壺上がり
オフセットインキで印刷中に壺の中のインキが流動性不良のためインキングロールに転移しなくなり、印刷濃度が低下する現象。
坪量
紙および板紙の重量表示方法で、一定面積当たりの重量で表示する。
壺ローラー
凸版、オフセット印刷機において、インキ壺を構成しているローラーで、間欠的に回転し、インキを呼び出す。
爪返し
枚葉印刷機において、圧胴、渡し胴など、紙の受け渡しの爪をカムによって開閉する機構。
艶紙
片面塗工紙にフリント光沢またはブラシ光沢仕上げなどを施して光沢をつけた紙。
艶消しアート紙
平滑性を高くし、光沢を低く仕上げたアート紙。
低温乾燥性オフ輪インキ
通常のオフセット輪転インキの紙面乾燥温度を10から20度低温にしたタイプのインキ。一般的には100~110度くらいの乾燥温度で印刷する。
停止円筒印刷機
平らな版盤と円圧胴からなる凸版印刷機の一つ。版盤のもどり行程中に圧胴が停止する。
デジタル印刷
原稿となる文字・画像などのデジタルデータをフィルムなどの中間媒体を使わないで直接刷版または被印刷物に出力する印刷技術。
ティンティング
印刷中、版面で起こる浮汚れの一つ。版面の非画線部にインキが薄くにじみ出たり、インキが付着するようになり、印刷物が汚れること。
手きん
フート印刷機を小型にして手動にしたもの。古くは名刺、はがきの印刷に使われたが、最近ではほとんど使われない。
手引き印刷機
手動印刷機の総称。凸版、平版、凹版それぞれに手引き印刷機がある。
デリバリー
印刷機の紙排出部。印刷を終えた紙は、枚葉印刷機では、くわえ棒にはさまれ、チェーンで紙積み台まで運ばれパイルされる。輪転印刷機では、折機で所定のサイズに折られた後、排出ベルトで機外へ出される。
テールエンドプリンター
フレキソ印刷機と加工機をインラインで組み合わせた印刷機。
点字印刷
2行3列に配列されている凸状の点を印刷により形成する方法。この点字は、点の存在をおもに指先で触りながら文字として読み取られるものである。
転写印刷
特殊印刷の一方式であり、材質・形状的に直接印刷しにくい被印刷体に印刷する場合、あるいは多色図柄を1回で被印刷体上へ形成する場合に用いられる。印刷には種々の版式が使用されるが、図柄の形成は転写紙上に逆刷りで行われる。
透過原稿
透過光で見ることができる原稿。主としてカラーフィルムのこと。
陶器印刷
陶器に絵付けを行う印刷の方法。スクリーン印刷による直接印刷方法と、特殊転写紙に印刷された図柄を陶器に転写し、焼成によって発色させ固定させる方法とがある。
謄写印刷
謄写版原紙をステンシルとして用いる孔版印刷。軽印刷分野で、経済性、簡易性などの利点のため小部数の印刷に適している。
当方紙
印刷物の受注のさい、印刷会社側が印刷用紙の購入、準備をすることをいう。出版社などの発注者が用意して支給するのを、印刷会社からみて先方紙というのに対する語。
透明インキ
光を透過するカラーインキで、とくに分散された顔料の粒子が小さく、ビヒクルとのぬれがよいインキ。下地を被覆する力は小さいが、プラスチックフィルムなどに印刷して透過光で見る色彩は鮮明で効果がある。OHP、カラーフィルター用印刷などに有用。
通し
印刷機の生産量を表す単位。通し数ともいう。1色機の場合は、通し数=印刷枚数となるが、4色機の場合は通し数=4×印刷枚数となる。
胴仕立て
枚葉オフセット印刷の版やブランケットの裏側に紙や布などを入れて胴径の大きさを調整し、適性な印圧、弾力性が得られるように仕立てること。
胴刷り
枚葉印刷機で印刷中、紙が供給されないのに圧胴を逃がし損ね、版またはブランケット胴が直接圧胴に当たり絵柄が転写されること。
胴逃がし
印刷機運転中にブランケット胴を逃がし、圧胴との接触を断ち印圧をなくすこと。
胴貼り
円圧式凸版印刷機の圧胴表面に紙、布、ブランケットなどを巻きつけて所定の胴の厚さに仕立てる。
胴貼り紙
円圧式凸版印刷機の胴表面に巻く紙。
胴枕
印刷機の版胴、圧胴、ブランケット胴の左右両サイドを輪状に高くした部分。
特色
イエロー、マゼンタ、シアン、墨の4色以外に、特別に調合された色。
とじしろ
製本のさい、平綴または穴あけのために用意する余白のこと。
ドットゲイン
印刷をするさい、印刷版の網点の面積が印刷物のインキの面積とは一致せず、一般には印刷物の網点の面積の方が大きくなる。この大きくなった状態をいう。印刷時の圧力が強い、インキが軟らかいとドットゲインは大きくなる。よい印刷再現を得るにはドットゲインをできるだけ小さくすることが大切である。オフセットの場合、輪転印刷は枚葉印刷と比べると大きい。印刷版を作る工程であらかじめ網点を小さく再現させておくことが通常行われている。
凸版インキ
凸版印刷に用いられるインキの総称であり、凸版の印刷版面から直接に紙その他の印刷素材に転移される方式に使われるインキ。
凸版印刷
凹凸のある版の凸部にインキを付け、紙などに押圧してインキを転移して印刷する法。
凸版輪転機
輪転版による凸版印刷機の総称。
扉
本の部分名。前付けの一種で見返しの次に位置し、書名、著者名、出版社名などを印刷する。
ドブ
「多面つけ」で印刷するときに、天地左右に接する印刷面との間に空きをとる必要がある。仕上がり線と製版線の間の裁ちしろを含め、大裁ちする場合に必要なこの空きをいう。
ドライオフセット
湿し水を使わないオフセット印刷で一般に凸版を使う。湿し水を使う一般のオフセットに対しての呼び方。
ドライダウン
紙への印刷直後の印刷物は、顔料、樹脂、溶剤がバランスよく塗膜を作るために光沢がよいが、乾燥する過程で一部の樹脂や溶剤分が浸透することによって印刷表面の光沢が低下する現象をいう。
ドライトラッピング
先刷印刷の完了後、乾燥したインキ皮膜の上に後刷インキを転移させることをいう。
ドライヤー
酸化重合型インキの乾燥促進剤。
トラッピング
多色印刷時における見当ずれにより、色の境界部分において下色などが現れてしまうことを防ぐため、隣接する一方の色を太らせて色を重ねること。
トンネル
乾燥ユニットのことで、フレキソ印刷機では共通圧胴型、スタック型供、印刷ユニット間のパスを短くしているため、その間の乾燥は次色の印刷に支障のない程度としている。そのためトンネルは、被印刷物の最終色を印刷後、まとめて全色を乾燥するように設置されている。
トンボ
製版、印刷工程で、工程内の品質管理の指標、印刷体裁の指標および製本加工の指標として使用するマーク。
長網抄紙機
走行するエンドレスの長い金網によって紙を抄造する機械。紙の材料は、この金網の上に流しだされて紙層を形成する。
流し貼り
凸版印刷機圧胴の上貼り紙をくわえ側だけを糊で固定し、流れ方向くわえ尻は固定しないで遊ばせておく。
長台印刷装置
手作業で行うスクリーン印刷にて使用する長尺の作業台。
中とじ
製本様式の一つ。週刊誌など比較的ページ数の少ないとじ様式に採用される。本文と表紙を同時に丁合いし、背側を表紙ともセンターページで2~3箇所固定する様式。
中本掛け
打返し掛けと、本掛けを混合した掛け方で、たとえば全紙24取りの場合、16ページを打返し掛けし、8ページを本掛けとして印刷するもので、片面刷りが終わったら8ページ分を裏版に取り替えて裏面を印刷する。
投込み
書籍の出版で、完成した本に挿入する印刷物をいう。
捺染
布地染色法の一つ。無地染めの浸染に対し、模様染めの技法の一種である。
捺染インキ
布地や繊維製品に絵付け印刷するインキで、直接印刷方式と輪転印刷方式とがある。
並製
雑誌、パンフレットなどにみられる仮とじをした製本様式。印刷された単一表紙で本文をくるむ様式。
2液反応型インキ
反応性樹脂をインキバインダーに使用している印刷インキと硬化剤の液状物質を印刷直前に混合して、印刷後に化学反応させ硬化乾燥させるインキである。
2回転印刷機
圧胴が連続回転し、平らな版が1往復する間に圧胴が2回転する円圧凸版印刷機。
2丁製本
二つ面付けされたものを、一つの単位として通常の製本工程を行い、丁合い後あるいは仮製本では製本完了後に2つに断裁し、同時に2丁の製本ができ上がる方法。
ニップ幅
印刷機の2本の円筒に、圧力をかけることによりできる接触幅。たとえばオフセット印刷機において、版の全面にインキをつけ、印刷機を停止状態でブランケット胴入れを行うと、ブランケット上に接触幅がうつされ、接触圧の大きさ、圧の幅方向の均一性を確認することができる。
2枚止め装置
枚葉印刷機において、フィーダーから紙が2枚重なって供給された場合、自動的に紙をとめる装置。
乳化
平版印刷で湿し水とインキが混ざり合い乳状になること。
入稿
印刷するための原稿を印刷会社へ渡すこと。
抜き型
紙器打抜き加工において、所要のカートンブランク形状に打ち抜き、筋付けを行うための、切れ刃と押し罫を備えた雄型。
抜刷
一冊の定期誌、書籍などのなかから必要な箇所を抜き出して、改めて印刷すること。
ネガタイプPS版
光を当てたとき、硬化するジアゾ系・ニトロ系化合物などの感光剤を、あらかじめアルミニウム・紙などのベースに塗布してあるオフセット印刷に用いる版材。
熱定着
熱融着性のある樹脂から成るトナー、印刷インキなどを紙に転写した後に加熱することによりトナー、印刷インキを紙に固着させること。
ねむい
印刷の階調の程度を表現する言葉。印刷で表現される濃淡の範囲が狭く、濃い部分と淡い部分の再現差が少ないことをいう。
納本
印刷会社が注文主に対し、印刷を完了した書物を納入すること。印刷会社が印刷を完了した書物の一部をクライアントに見本として納めること。
ノーカーボン紙
カーボン紙を用いずに複写を行う紙。
のこ刃
巻取紙輪転印刷機折装置の紙をカットするのに用いられるのこぎり状の刃。
のせ
印刷の際に下地に平網処理をした色の上に、文字やロゴなどを刷る重ねること。
のど
本の部分の名称であり、本の中身の背に接する部分、またはとじ目の側。
糊しろ
折丁を貼り込む場合、糊のつく部分としてのど側に残した余白部分。糊しろのない折丁(のどのきわまで印刷した折丁)は、これを貼り込んだときに印刷インキの樹脂分が糊をはじいて接着力が弱くなり、はがれてしまう。
ノンブル
本のページ付け、またはそのページ番号。
倍胴型
ユニット型枚葉多色オフセット印刷機において、前の印刷ユニットの圧胴から印刷紙を受け取り、次の印刷ユニットの圧胴に渡すための胴において、胴径が版胴の倍径のものを倍胴型という。
ハイファイカラー
あらかじめグラビア輪転機などでカラー印刷された巻取り紙の裏面に、新聞輪転機でニュースを追加印刷する方法。記事の印刷と裏面の絵柄との見当合わせは行わず、どこで断裁されてもよいような絵柄に限定される。
ハイライト版
挿絵などの白地に調子のある原稿を製版する活版用の原版。
パイルデリバリー
枚葉印刷機の排紙部で、印刷紙を積み重ねる装置。
パウダースプレー装置
主として枚葉印刷機の印刷部を出た後に、パイルによるインキの裏移りを防止するため、澱粉、タルクなどの微粉を印刷面に散布する装置。圧縮空気を利用して、印刷面に少量均一に散布する。
箔押し
表紙に直接金箔、色箔などを接着すること。
箔押し機
表紙に金箔、色箔などを押す機械。
白化
溶剤型グラビアインキ、フレキソインキで印刷したフィルムを乾燥させるさい、インキ表面が冷えて空気中の湿分がインキ膜中に混入して白っぽくなる現象。
バックアップローラー
グラビア輪転印刷機の圧胴を上からバックアップし、圧胴のたわみによる押圧の逃げを防ぎ、全体に強い印圧をくわえるためのローラー。最近の印刷機では、圧胴の内部構造に工夫をしてたわみによる圧の逃げを防止し、バックアップローラーをなくした印刷機もある。
ハード・プルーフ
ディスプレイ画面で見られる「ソフト・プルーフ」とは異なり、紙に印刷したモノクロやカラーの校正刷りをいう。
花布
上製本において、本文の背の部分の天地両端に貼り付ける小さな布。
パーフォレーション
印刷機を用いて刷本に切り取り用の線状の小さな穴をあけること。印刷機の版面に穴あけ用の刃を組み付けて、印刷と同時に穴をあけすることもあるが、ブランケットなどに傷がつき、色数も制限されることから、印刷とは別の専用ユニットを設けて穴あけをする場合が多い。
端物
はがき、伝票、名刺、表類など、ページ物でない、体裁の一定しない印刷物。
端物印刷機
少量部数の印刷に適した小型印刷機。
針
枚葉印刷機フィーダー上で、紙の横方向を規制するための金具。紙は印刷ユニットに入る直前、まず前当てに当ててから横に引き、印刷位置を一定に決める。
針金とじ
仮製本のとじ方の一つで、針金を用いて本をとじ付けること。
貼込み
別の種類の折丁を貼り合わせること、折丁ののどの部分に糊を引いて貼り合わせる。
針印
枚葉機で印刷するさい、刷位置のずれの有無を見るため紙の余白部に入れた小さなマーク。正常に印刷されているものはマークの位置が紙の端から一定の位置にあり、連続して印刷紙を検査する場合、位置ずれのあるものは容易に発見できる。
針しろ
巻取紙印刷の折丁の端から針穴までの距離。
針違い
紙の上で正常な印刷位置からずれて刷られたもの。枚葉紙は前当て、横針りに当てることによって前後左右共印刷位置が規制されるが、連続印刷中、突然、正規に当たらなかったりすると針違いが発生する。
バレープリント
別名谷染め印刷ともいう。型押しと同時にその凹部にも色付けを行う印刷で、合成皮革、壁紙などの印刷に用いられる。一般的には熱可塑性の被印刷体を予備加熱し、凸部にインキ着けした彫刻版などの版胴で被印刷体にエンボスを施すと同時に被印刷体の凹部に色付けを行う。
版かぶり
グラビア印刷時の故障の一つであり、画線部以外の箇所にドクターでインキが掻き切れない部分がしょうじ「かぶり」となって印刷物に転移する現象。
番号印刷
紙幣、株券、手形、債券などの有価証券や、事務用帳票、送り状などの伝票類に番号を印刷すること。通常は印刷機械に番号器を組み付けて、紙が1枚通るごとに自動的に連続した番号を印刷する。
反射原稿
通常の光が原稿に当たり、その反射光で画像が認識されるとき、その原稿をいう。
版シリンダー
印刷機の版胴となるシリンダー。凸版、オフセット印刷では版シリンダーは印刷機に固定されており、板状の版を別工程で作り、版シリンダーに固定する。グラビア印刷では巻き取り紙用は版シリンダーを取り外して製版し、印刷機に取り付ける。枚葉グラビア印刷では凸版、オフセット印刷同様、固定シリンダー方式となっている。
版づら
印刷物の判型から周囲の余白を除いた、本文や見出しの活字・罫線類が印刷される部分を版づらという。
パントンカラー
米国のパントン社の商品名で、印刷物やデザイン製品などの色彩決定に用いられる。
版残り
印刷中に、版、ブランケット、ローラー面にインキや紙粉がパイルする現象。
版離れ
スクリーン印刷において、印刷時に発生する現象。
PS版
プレセンシタイズド・プレートの略で、平版刷版の材料として世界中で幅広くしようされている。版材の支持体としてはアルミニウムが一般的であり、版面強度など印刷適性をいちだんとアップさせるために、表面を陽極酸化したアノダイズトタイプが主流になっている。
非画線部
印刷版面のうち、印刷インキの付着しない部分。
引合せ
校正において、初校の校正刷で書きいれた赤字どおりに、再校で差し替えられ、正しく訂正されているかどうかを調べること。
引き針
枚葉印刷の場合の紙差し法の一つ。印刷機の見当部の前当てに紙が当たった直後に、操作側の横針に引き当てて、紙の位置を規正する紙の差し方。
ビクトリア印刷機
平圧式印刷機の一種。圧盤が版盤と平行の位置をとる平行押圧式で、印刷圧力も強大で、平均に加えられる構造となっている。
ひげ
印刷物の不適正なしあがり効果の状態を表現したもので、画線部の周囲に短いひげ状に発生したインキのはみ出し。
ひじわ
オフセット輪転印刷機において、ドライヤー加熱の影響により発生する波状の用紙のしわ。
ヒッキー
印刷物がところどころ環状に抜ける現象。版面あるいはブランケット表面に異物がついた状態のときに発生する。
ピッキング
インキの粘着力が紙の表面強度より強いときに発生する紙むけのこと。
非塗工紙
コーティングされていない紙をいう。代表的なものに「中質紙」「上質紙」などがある。
ヒートセットインキ
平版、凸版の高速輪転印刷用に用いられるインキで、加熱によってインキ中の溶剤が蒸発し、瞬時に乾燥するインキ。現在は平版輪転印刷で多く使われており、高速印刷での乾燥をよくするため、ビヒクルとして低沸点パラフィン系石油溶剤に溶解したロジン変性フェノール樹脂を用いる場合が多い。
ビニル貼り
フィルム貼りの一つで、薄い塩ビフィルムを貼ることにより、印刷物の表面を保護するとともに、光沢を与える。
ビニルフィルム印刷
塩化ビニルを主体としたフィルム上への印刷。
B-B型オフセット輪転機
2本のブランケット胴が巻き取り紙をはさんで並び、表裏同時印刷可能な構造を有するオフセット輪転機。
平網
一定割合の網点が並んでいる均一濃度のパターン。
平台印刷機
一般的には輪転機など丸版使用の印刷機に対して、平らな版を版盤にのせて円筒形の圧胴で押圧しながら印刷する機械をいう。
平台グラビア印刷機
銅板に製版したグラビア版を平台印刷形式の版盤にのせ、ドクターを用いてグラビア印刷する機械。グラビア印刷の初期の機械で、現在は使用されていない。
平とじ
仮製本のとじ方の一つ。中身ののどの近くを側面から針金でとじるとじ方。簡便なとじかたであり、雑誌などに広く用いられる。
ファーニッシャーローラー
グラビア印刷機のインキ供給装置の一つで、インキパンから版面へインキを供給するためのゴムローラー。
ファンシーペーパー
美しい意匠を施した装飾用紙の総称。艶紙、マーブル紙、パール紙、型つけ箔押紙、レース紙、シルクスクリーン印刷紙、花模様印刷紙などがある。
フィーダー
=自動給紙機
フィードローラー
枚葉紙印刷機。折り畳機などの自動給紙機において、一枚一枚分離された紙を本体に正確に送り込むためのローラー。
フィラーシート
凸版印刷機の胴貼り紙のうち、自由に抜き差しできる紙のこと。
フォトタイプオフセット印刷
軽印刷の一種で、PTO印刷ともいう。写真植字による直接フィルム、あるいは文字貼りこみ台紙を原版として、直接刷版を製版しオフセット印刷を行う。
フォーミング
巻き取り紙輪転機において印刷されたウェッブを縦に連続的に折り重ねること。
フォーム印刷
事務手続、事務管理などに用いる書式の決まった帳票を印刷する方法。印刷方式としてはオフセット方式、凸版方式、フレキソ方式、グラビア方式がある。
フォーム印刷機
電子計算機用の連続伝票を印刷すると同時に、ミシン、ジグザグ折などの後加工を行う装置を連結した巻き取り紙輪転印刷機。印刷版式は合成樹脂またはゴム凸版、オフセット版を用いる。連続伝票は、印刷の裏表見当精度以外に、横ミシンを基準として印刷の天地見当、パンチ、折り位置の精度を要求される。
袋
紙折機または輪転印刷機の折機により、印刷物は折りたたまれる。この折られたものを折丁とよぶが、この折丁において小口の一部が折り目になった部分をいう。
袋掛け
刷り物を折ったときに小口が袋になるような版面の掛け方。
不織布
天然、再生、合成などの繊維を単独または混合して接着剤などで接着して布状にしたシート。
フート印刷機
足踏み式平圧印刷機。機械のペダルを足で踏むと、版面にインキをつけ、圧盤が動いてきて版面を押圧して印刷する。
ブラインデング
印刷中に画線部にだんだんインキが付着しなくなり、濃度が薄れてくる現象。印刷時に繰り返し版面にくわえられるローラーやブランケットの摩擦圧などで画線部がしだいに破壊される。
ブラッシング
グラビア印刷での品質トラブルの一つ。グラビア印刷されたインキがフィルム表面で乾燥するさい、印刷面の光沢不良や不透明となり、スクラッチ不良や接着不良が生じること。
ブランケット巻き棒
凸版印刷機やオフセット印刷機において圧胴またはゴム胴にブランケットを巻きつけて張るための棒。
フランス装
糸とじした本文を立方体のまま仮固めしておき、これに、本文より30~50mmほど大きい表紙用紙の四方の角を折り返して糊貼りし、表紙貼りの代わりとしてくるみを行った様式。
フランス表紙
=フランス装
ブリスター
オフセット輪転印刷においてヒートセットインキを使用するが、乾燥部でアート紙やコート紙のコート面の一部が膨れあがって火ぶくれを起こす現象。
ブリスタリング
印刷物の印刷基材上またはインキの膜面に発生するふくれのこと。
ブリード
印刷インキに含まれる顔料が印刷時または印刷後に溶剤、油脂、可塑剤や水などに溶けて色がにじみ出てくる現象。
プリプレス
印刷の前工程の総称。
プリントスルー
印刷物の文字や絵柄が裏面から透き通して見える現象をいう
フレキソ印刷
凸版印刷の一種で、フレキシブルな樹脂またはゴム凸版を用い、溶剤乾燥型インキを用いた印刷方式。
フレキソ印刷機
アニロックスロールと称するインキ着けロールと速乾性インキとによってゴムまたは合成樹脂凸版の印刷をする輪転印刷機。
プレスコート
表面加工の一つで、印刷物表面に高級感のある滑らかな鏡面光沢を与える加工法。
プレートグラビア
枚葉グラビア印刷機に使用されるシート状のグラビア版。
プロセスインキ
カラー原稿を黄版、紅版、藍版、の3色に墨版を加えた4色刷により、色再現が可能な組み合わせのインキ。
ブロッキング
印刷インキの乾燥するプロセスのなかでインキの粘着性のために印刷物が互いに接着する現象。
文化用紙
産業用紙に対して用いられる用語。筆記および各種の印刷用紙を含んでおり、文化目的をもって使用される用紙のすべてをさす。
噴射インキ装置
グラビア輪転印刷機の版胴の表面にインキを吹きつけ、または、かけ流しする装置。
分色校正刷
カラー印刷は4色の重ね刷りで表現するが、印刷サンプルとなる校正刷は半自動機で1色ずつ刷り重ねていく。このとき1色ずつ単独に印刷したもの、および2色、3色と刷り重ねのプロセスの各段階の校正印刷物をいう。
平圧印刷機
平な版に対して平らな圧盤によって紙に押圧を加えて印刷する形式の凸版印刷機。
平版
印刷版式の一種。版面に明確な高低差がなく、画線部は新油性、非画線部は親水性で、版面に水とインキを交互に与えると水と脂肪が反発しあう性質を利用して印刷する方法。
平版印刷機
平版の印刷に用いる印刷機の総称。オフセット印刷機と、直刷印刷機とに分類される。現在では直刷印刷機は石版印刷機だけで、ほとんどがオフセット印刷機であるため、オフセット機のことを意味する。
平版グラビア
通常グラビア印刷機は版胴から直接紙などに印刷するが、平版グラビアでは版胴から印刷紙などに直接印刷されず、版胴と接しているゴム胴に一度転移させた後、被印刷物に印刷する方式で、合板などの厚い被印刷物の印刷に使用される。
平面印刷機
紙、フィルムなど、平面形状の被印刷体に印刷するスクリーン印刷機。曲面印刷機に対する名称。
ページ物
ページ数の多い、体裁の一定した印刷物で、端物に対していう。組版仕様が一定している読物である書籍が代表される。
ベタ
印刷の濃淡は網点の大小で再現させるが、網点面積100%すなわち全面にインキがついている状態をいう。
別丁
本文中あるいは本文の前後にとじこんだり、はりこんだりする本文とは別刷りの付属の印刷物。口絵、扉、中扉、折込などを総称していう。
ペラ丁合い
1枚ものの印刷物(ペラ)を丁合いすること。
坊主
売り上げカードの俗称で、書物に挿入されているカード。注文カードと表裏になっている短冊形で、書名、定価、発行所、書籍コードなどが記入されていて、書店が販売の整理に利用するもの。
包装紙
包装に使う紙の総称。包装適正の優れた丈夫で耐水性のある両更クラフト紙やロール紙、または印刷適性の要求される商業用には晒クラフトなどがある。
補色
二つの色光を合成したときに、白色光になる二つの色の関係をいう。たとえば、シアンと赤、マゼンタと緑、イエローと青の関係を互いに補色という。
補刷
印刷が終了した時点で、印刷物に脱落また色調の再現ミスなどが生じた場合、再度その印刷物に刷り加えること。
ポリエチレンフィルム印刷
ポリエチレンの表面には活性基がないため、インキの接着が悪い。そのためコロナ放電処理を行ってから印刷する。印刷はグラビア印刷、フレキソ印刷が一般的。
ホログラム
光の干渉を用いて物体の情報を記録したもので、照明すると回析により立体像が再現できる。
ホローバック
上製本の背固めの一種で、本を開いたときに表紙と本文の間に空洞ができるのが特徴。
本掛け
印刷機で表版と裏版を別々に組み付けて、折丁単位で面付け印刷する方法。
本機刷り
校正刷りを行うために使う校正機ではなく、本番の印刷で使う印刷機で印刷すること。オフセット印刷の場合、校正機は平らな版、圧胴に円筒状のブランケット胴でインキを転移させ紙に印刷するのに対し、本機は円筒状の版、ブランケット胴、圧胴を使用して印刷する。
本紙
最終製品となる正式の用紙で、本刷りに用いる用紙。印刷会社では、試刷紙・校正紙・調肉紙などに対して使う。
本刷
印刷機に版面を取り付けて、見当、色調などの調整を行い、機械校正を終了し本紙に印刷すること。
本製本
製本法の一つ。中身を糸でとじあげてから、別に仕立てた表紙をつける方法。
ボンド紙
化学パルプを主体として、叩解しサイズを配合して抄造した良質の用紙。
マイグレーション
印刷物を巻取りまたは重ねた場合に、インキ皮膜に接した基体の背面部にインキ成分が移行して変色する状態。
枚葉紙
抄造後に一度巻きとられた紙が、再び菊判、四六判など適当な寸法に断裁された紙葉。巻き取り紙に対比して用いられる。印刷は、枚葉給紙型印刷機で行われる。
枚葉紙印刷機
枚葉紙に印刷する印刷機をさし、凸版、オフセット、グラビアの名を冠するのが一般的。巻き取り紙印刷機に対していう。
枚葉印刷方式
枚葉とは紙の形態をいい、全判・半裁・4裁などの大きさに断裁した用紙をいう。枚葉印刷は1枚1枚の紙を印刷機に通して印刷する方式で、輪転印刷に対していう。
枚葉紙グラビア印刷機
枚葉紙に印刷するグラビア輪転機。
枚葉紙凸版輪転機
枚葉紙に印刷する凸版輪転機。
前当て
枚葉印刷機の給紙装置で、紙差しのさい、紙の前辺の位置を定め、印刷の前後方向の見当を正しくするためにの紙差しゲージ。
前印刷準備
平台印刷の版は一般的に1ページ単位のもので、印刷機の運転能率を考慮して、本機に掛ける前に校了機の指定に従って版を組み付ける。印刷物の折り方のひとつで、折丁を作るさいに一辺に平行に同じ方向に2回以上折る折り方。
巻折掛け
折り方の一種で、版を一方向に並べて印刷し、これを中心から二つに折り、さらにこれを同じ方向に再度二つ折りにする方法。
巻取紙
輪転印刷機による印刷に適合するよう、抄造後、巻取心棒に連続に巻いて仕上げた紙。
巻取紙印刷機
巻取り紙に印刷する印刷機の総称。凸版用、オフセット用、グラビア用などがある。枚葉紙印刷機に対していう。
巻取紙平圧印刷機
平圧印刷機の能率を上げるために、巻き取り紙を使ったもの。
巻取紙輪転印刷機
輪転印刷機の能率を上げるために、巻き取り紙を使ったもの。
巻取り装置
巻取り紙輪転印刷機で印刷された印刷物をウェッブのまま巻き取る装置。
膜面
カラーフィルム、白黒フィルムなど写真感光材料の感光膜が塗布されている面。
マージン
書籍などの各ページの、本文や見出し類が印刷された部分の周辺にできる余白部分。
マシン仕上げ紙
抄紙機に連結されているカレンダーにより光沢をつけた紙であり、大部分の印刷用紙はこれに属する。
マスキング
多色印刷をするさい、カラー原図の色調や階調を忠実に再現するために、写真製版工程において各種の修整を行うこと。
マスターペーパー
おもに軽印刷に用いられる紙をベースにした印刷版の総称。電子写真法か銀塩写真法によりダイレクト製版にて版を作る。
マットインキ
印刷仕上がり面に光沢がでない印刷インキ。一般に、油性のビヒクルを用いた印刷インキは相当の光沢を有する。
丸背
製本において、上製本ものの背の仕立て方の一種。背中に丸みをもたせる方法。
丸版
輪転印刷機に使われる湾曲した版。
回し刷
全紙に対して版の数が半分しかない場合、機械の片側に版をセットし紙を回しながら表裏を印刷する。
見返し
本の中身と表紙とをつなぐために、表紙の内側に貼る紙。
水切り
オフセット印刷機の湿し水装置で、版面全体に均一に水をつけるために、水元ローラーの表面をなでて湿し水を調節する器具。
ミスチング
印刷機の回転中に機上からインキが噴霧状になって飛散する現象。とくに高速輪転印刷機に多く発生する。
水なしオフセット
一般のオフセット印刷は、水と油の反発作用を利用した印刷方式、この「水なし」方式はシリコンなどのインキ反発性物質を刷版上の非画線部に形成することにより、画線部だけにインキが付着し印刷ができる。
水幅
オフセット印刷ではインキと湿し水が混和されて版面に供給され、画線部にインキが付着し印刷が成立する。この場合、絵柄面積によって供給される水の量が異なるため、条件によってはインキと水の混合比が必ずしも一定ではない。したがってインキとしてはある程度水を絞っても地汚れが生じないこと、多くても乳化して水負けするようなことのないインキが求められる。すなわち、インキと水が接触して印刷適性を保持する上限から下限までの湿し水の混合幅をいう。
水負け
印刷インキが湿し水によって過度の乳化状態となり印刷適性を失う現象。
見開き
書籍などで、収容すべき罫表または、図版が大きすぎるか、または割付の指定により、1ページに収まらない場合には、分割して向かい合った2ページにまたがって入れる。このような印刷物またはその版面を見開きという。
ミーレ印刷機
代表的な2回転印刷機。圧胴が版盤の帰り工程にも回転し続け、版盤の1往復に圧胴が2回転する円圧印刷機。
むしり
打ち抜きの後、不要部分を除去する作業。
無線とじ
丁合いされた刷本を針金とじせずに接着剤だけで折丁の背を結合する方式。電話帳や各種単行本のほか、一部の雑誌に採用されている。
無停止給紙機
枚葉印刷機に紙を補給するさい、機械を止めずに新しい紙を補給することが出来る自動給紙装置。
メカニカルオーバーレイ
凸版印刷のムラトリ方法のうち、手工的方法によらないものを総称した呼び方。
メークレディー
版の部分的な印刷圧の不均一を補正する目的で版に施す操作のこと。
メジューム
インキ用ワニス単独、または白色顔料のみを分散した無彩色希釈用インキ。グロス向上、マット化など特殊用途もある。
メタルベース
印刷するさいに、鉛版、樹脂版、電胎版などを組み付ける金属製台で、一般的には軽金属が材質となっている。
滅活字
印刷や紙型取りなどによって、字づらが摩滅して使えなくなった活字。
面掛け
用紙の片面に印刷されるページ数。ページ数によっては同じものを2通り、4通り掛けする場合もある。
面付け
製本工程における折加工で折本が正しいページ順になるように、原版を貼りこむこと。
モアレ
幾何学的に規則正しく分布した網点、または線が重なり合ったときに生じる斑紋もことで、重なり合うスクリン角度が15度以下になると、モアレ模様がめだつ。
木版印刷
東洋では7世紀半ば頃より中国経典や暦本が木版印刷によって行われ、わが国の百万塔陀羅尼経文は現存する最古の木版印刷物とされる。
木矢
凸版印刷の組み付け作業に使用するくさび状の木製の板。
盛り上げ印刷
凹型を用いずに画線部を隆起させる印刷法。印刷機で印刷したインキが乾かないうちにパウダーを散布し、余剰のパウダーを除却する。さらに加熱することによりパウダーを溶着、隆起させる。透明パウダーを用いることによって各色の盛り上げが可能である。
盛り上げ印刷インキ
印刷面が隆起状に仕上がる印刷インキ。
モルトン
オフセット印刷における湿しローラーにかぶせて使用する綿のタオル状の被覆材。きわめて保水性がよく、均一に水を与えることができる。
焼き落とし
平版の刷版を製版する場合、不要な絵柄、濃度管理用ケージ、見当合わせ用トンボ、汚れの原因になる非画線部など、原版で不必要な部分をマスクを使用して露光・消去すること。印刷するさいに、必要な画線部以外の汚れをできる限り除去するために焼き落とし作業を行う。
焼き込み
感光膜を有する版材、フィルム、印画紙などに、原板を密着または拡大・縮小して露光するさい、原板のもつ階調を意図的に変化させるために露光量を調整すること。
焼き度
写真平版刷版において、露光した場合の焼付け度合い。
ヤレ
印刷し損なった印刷用紙の総称。
UCRマスク
原稿のグレー部分から3色のインキ量を少なくし、墨を代わりに印刷する方法で使用するマスク。
ユニット
ひとまとめの単位のことで、印刷機械では一組の版胴と圧胴によって1色刷りを行う印刷装置。オフセット印刷機では、版胴・ゴム胴・圧胴の3胴で一組となる。
ユニバーサルフィーダー
小型・低速の枚葉印刷機に用いられる吸いつけ式自動給紙機の一種。
用紙の印刷適性
印刷適性とは、印刷の仕上がりに欠くことができない、紙やインキなどの印刷材料に求められる性質をいう。その代表的なものが紙の印刷適性である。
羊皮紙
羊、やぎなどの動物の皮革で作られた書写材料。紀元前2世紀ごろから、欧州、小アジア地方で用いられ、現在でもまれに貴重文書の書写、印刷に使われる。
横当て
枚葉印刷機で印刷する場合、紙を版に対して一定の位置に正しく置き定め、印刷の左右方向の見当を正確にあわせるため、紙差しのさい、紙の横縁の位置を決める当て。一般印刷機の場合、まず前当てに紙のくうえ端を当て、つぎに横当てに紙の横縁を当てる。この場合、紙の縦横の直角度の正確な方を使用するため、印刷機の操作側の横当てに引いて当てる場合と、駆動側の横当てに押して当てる場合とある。
横断ち装置
巻き取り紙印刷機でウェップを横に裁って枚葉とする装置。
横通し
巻き取り紙印刷機で印刷しうる紙幅が、印刷用紙の原紙規格判寸法の横幅寸法となっている場合の呼称。この場合、巻き取り紙印刷機のシリンダー幅は原紙規格判寸法の横幅寸法となる。
横針
枚葉印刷機で印刷する場合、紙差しのさい、紙の横縁の位置を定め、印刷の左右方向の見当を決めるための基準となる金具。一般印刷機の場合、まず前当てで前見当を決め、つぎに横見当を決める。
横振りローラー
凸版やオフセット印刷機のインキ装置において、インキの練りならしをするためゴムローラーと組み合わせて軸方向に動く金属ローラー
四つ折り
折り方の一種。まず半分に折り、その折り目に直角に再度折って、8ページとする折り方。
読み合わせ校正
対校ともいい、2人が1組となり、1人が原稿を読み、1人が校正刷りを見ながら校正する方法。
ライダーローラー
凸版やオフセット印刷機のインキ装置においてゴムローラーと組み合わせてインキ練りを行うための金属ローラー
ライトテーブル
テーブルの表面にすりガラスをはめて、内部に蛍光灯をつけた机。
落丁
ページ物を丁合いするさい、折丁の一部が足りないまま製本された状態、または印刷物が指定の部数だけ完成しないこと。
落丁刷
製本の時、注文部数だけできなかった場合、折丁の不足分を追加刷りして不足部数の製本を行うこと。
ラップアラウンド版
高速輪転印刷をするとき、版胴に巻きつける凸版であり、薄い金属版および感光性樹脂版が用いられている。
ラフカンプ
デザイナーが仕上がりのイメージをクライアントに理解してもらうために作成する写真・イラスト・文字の位置・大きさをラフに指定したカンプ。写真やイラストは他の印刷物で使用しイメージに近いものをダミーで使用するなどカンプより完成度は低い。
乱丁
製本作業上の誤りの一つ。丁合いしたとき、一冊分の折本のある部分が順序不同になった場合をいう。
リソグラフィー
かつては、平版印刷と同義であったが、現在では石版石を版材とする平版印刷を意味することが多い。
立体印刷
立体画像を再現する印刷。アナグリフ法、レンティキュラーレンズ法、ホログラフィーなどがある。
リボン式折機
巻取り紙輪転機の折り装置の一種で高速運転に適する。
流用版
一度使用した広告や図版などを保存しておき、他に流用すること。
両面印刷機
1回の印刷通しで表と裏両面を印刷する印刷機。巻き取り印刷機の表裏印刷は普通であるので、一般に枚葉紙印刷機をさす。
輪転印刷
各版式に用いられる印刷方式で、版も用紙も円筒に巻きつけ、双方を回転させながら連続的に印刷する方式をいう。凸版輪転印刷機とオフセット輪転印刷機、グラビア輪転印刷機などがあるが、近年の輪転印刷機は両面4色が印刷できる方式が主流になっている。
ルビ
ふりがな用活字、またはふりがなのこと。五号活字のふりがなである七号活字が、欧文活字でルビーと称されていた約5.5ポイントの活字とほぼ同じ大きさであったことからきている。
レイテストニュース装置
新聞輪転機につける、追加記事刷りこみ用印刷装置。取りつけは本機の圧胴を用い、版胴は本機の1/2径とするものが一般的である。本印刷で空白にしておいた部分に刷りこむかあるいは本印刷上に色インキを刷り重ねる。
レインボー印刷
印刷で用紙の一方向を複数の色で刷り分け、かつ隣り合った色間をにじませ虹色のように表現する方法。印刷機のインキ壺内に複数の堰を作り複数色のインキを各々の堰で仕切られた区画に入れ、インキ装置の横振りを止め隣あったインキの境界をにじませて印刷する。
レーザー製版
カメラ、焼枠などを使わずにレーザービームを電気的に制御して直接印刷版を作る製版方法。
レジスターマーク
見当合わせに用いるマーク。4色の色および原版を重ねたとき、その位置精度が正確に重なっているかを目視およびルーペを使用した目視で確認するためのマーク。
レジューサー
印刷インキの固さや粘りを調整するときに加える、一種の希釈剤。
レターセット印刷機
活版印刷をオフセット印刷と同じようにゴム胴に印刷してから圧胴によって紙に移す方式の印刷機。
レタッチ
製版作業において、色分解された写真原稿のフィルムの調子再現を変更するため、増減力処理を施すこと。
連
紙および板紙の取引上の一単位。わが国では平判の場合は規定寸法に仕上げた紙1000枚、板紙の場合は100枚を一連とする。
連続階調
写真原稿、グラビアコンペンショナルなど、連続的に濃度の変わる階調。
連続伝票用紙
コンピュータ処理の最終結果の記録に用いられる紙。
連続封筒
封筒が連続的につながった状態のものであり、ミシン目などで折られている。
練肉機
印刷インキを製造する機械の総称。顔料をビヒクル中に練和分散させる機械で、代表的なものは3本ローラーミルで主として粘度の高いオフセットインキの製造に用いる。
連量
1連の紙の重量。わが国ではキログラムで表す。
ロータリースクリーン印刷機
シリンダー状のスクリーン版を使用し、被印刷体の移動にあわせて版を回転して印刷するスクリーン印刷機。印刷速度が速く、継ぎ目のないシームレスの画線を印刷できることが特徴。
ローラー洗い装置
印刷終了後、印刷機からインキローラーを外さずにインキを短時間に洗い落とす装置。
ローラー飛び
凸版やオフセット印刷中にでる縞状のムラ。
ローラー目
凸版やオフセット印刷中に生じるムラで、インキ着けローラーの円周長を1周期として印刷方向と直角にできる。
ロールコレーター
丁合い機の一種類で巻き取り状の用紙を複数枚重ねる機械。おもにフォーム印刷の製品仕上げに用いる。
ロール紙
ヤンキーマシンで抄いた片艶の紙で、印刷用紙、包装用紙に使われる。
ワイピング
彫刻凹版などの印刷において、版面に着けた余分なインキを拭き取ること。凹版輪転印刷機においては、インキ着けされた版面がワイピングペーパーの巻き取り紙にこすられて版面の過剰インキが除去される。
渡し爪
印刷紙を前の工程からひきはなして次の工程へ導きわたすための爪。枚葉紙オフセット印刷機のフィーダーより圧胴へ紙を渡すスイング装置の爪がこれである。
渡し胴
ユニット型枚葉紙多色オフセット印刷機に用いられている機構で、前の印刷ユニットの圧胴から紙を受け取って次の印刷ユニットの圧胴に渡すための胴。
渡り
組付けのさい、のどを中心にして左右に並んだ2ページの版の、左側の版の左端から右側の版の右端までの寸法。
和本
昔から日本で行われている製本形態で、手作業で糸を使ってとじた本。
割付
組版作業を行うために、印刷物の判型のスペースに文字郡や図形、写真などの配置を決めることをいう。
ワンタイムカーボン紙
カーボン原紙にカーボンインキを全面塗布して作った複写紙であり、1回ごとの使い捨てである。
ワンプ
製紙工場、印刷工場などで用紙、印刷製品などを包装するのに用いる低級紙の俗称。